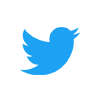子どもに生成AIを使わせるなんて…。宿題を肩代わりさせたりとか、嫌な予感しかしないわ!
メリットとデメリット、両方を知って活用していくのが、現代の必須スキルじゃ!
- 田中博之さん

-
早稲田大学教職大学院教授。1960年北九州市生まれ。大阪大学人間科学部卒業後、大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程在学中に大阪大学人間科学部助手となり、その後大阪教育大学専任講師、助教授、教授を経て、2009年4月より現職。主著に、『教師のためのChatGPT活用術』学陽書房、他多数。研究活動として、生成AIの教育利用の研究等、先進的な研究に従事。
近年、ChatGPTなどの生成AIの技術が急速に進化し、小中学生の子どもたちが生成AIに触れる機会も増えてきています。生成AIは、学習の効率性向上や問題解決に役立つ一方、ハルシネーション(誤情報の生成)を起こしたり、生成AIに依存したりすることにより、子どもたちの思考力や創造力の低下につながることを心配する声もあります。今後ますます生活に深く関わってくるであろう生成AIを、子どもたちが使用するメリットとデメリット、生成AIと賢く付き合っていく方法を、早稲田大学教職大学院・教授の田中博之さんに伺いました。
生成AIとは何か?仕組み、教育現場での活用事例を分かりやすく解説
生成AIとはどのようなものなのか、また、教育現場でどのように活用されているのか伺いました。
生成AIとは「創り出すAI」

——生成AIは、従来のAIとは何が違うのでしょうか?
田中:まず従来のAIから説明します。AI とは、Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス/人工知能)の略称で、人間がこれまで長い時間をかけて学んだり、明らかにしてきた知識やデータ、ルールをもとにして、判断や制御をするコンピュータのプログラムを学習したものです。
これは私たちの生活で既に活用されています。わかりやすい例が、ルンバなどのロボット掃除機です。ロボット掃除機は、障害物を避けながら掃除をして、充電器のある場所に戻っていきます。つまり「AI(人工知能)が状況を判断して、動きをコントロールしている」わけです。
それを踏まえ、生成AIはこれまでのAIと何が違うかと言うと、「何かを生み出す、創り出す」という点ですね。文章、音楽、動画などを生成できます。
しかし、何かを生み出すには、すでに世の中に存在している名作や名曲などの「それまでのもの」を知らないと良いものは作れないですよね。何も蓄積がない状態では名曲は作れません。ですので、生成AIは、世界中のインターネットに載っている知識や情報、世界中にある本、あるいは論文など、ものすごい量を常に勉強しています。
このようにして生成した文章や画像、音楽などによって、人間の知的作業をサポートすることができるようにしたコンピュータの新しいプログラムなのです。
教育現場での生成AIの普及はまだまだ手探り?
——現時点(2025年8月)で、教育現場での生成AIの利用はどのような状況なのでしょうか。
田中:公立の小中学校だと、一部で先進的な取り組みをしている学校もありますが、まだほとんど使われていません。一方、私立学校は進んでいる傾向ですね。
——生成AIの学校での活用事例について教えてください。
田中:「総合的な学習の時間」という、児童・生徒がさまざまな課題を調べて発表する科目があります。小学校中学年では「地域について調べる」という課題の際に、生成AIを使って、地域のオリジナルご当地ゆるキャラや地域のオリジナルソングを作った例があります。結構それっぽいキャラクターや曲が作れるんですよ。
そのほかに、小学校の取り組み例としては高学年の「道徳」の時間での活用があります。道徳って、どうしても堅苦しいといいますか、道徳的な物語に基づいた「望ましい答え」が決まっている世界ですよね。優等生の子がよしとされ、乱暴者のガキ大将をよしとしないような。
ただそれではちょっと面白くないので、ガキ大将が言いそうな意見とか、ズル賢い取り巻きやゴマすり役が言いそうな意見を、生成AIを使ってあえて作らせてみる。深い道徳的な判断力を育てるには優等生だけがいてもダメなわけで、生成AIを通じて多面的に物事を見ることをアシストしています。
ほか、道徳では「司会者」を生成AIに任せる事例もあります。グループワークで5つも6つもグループができたら先生一人でまとめきれないですからね。
生成AIが塾代わりにも!「教科書からテスト勉強用の問題を作って」

田中:こちらは学校での取り組みというより生徒の自主的な使い方ですが、中学生になると、テスト対策で生成AIを活用しているケースもありますよ。
教科書を撮影し生成AIに読み込ませ、「これを基に中間テストの試験問題を作って」と指示するわけです。穴埋め問題や長文読解などの出題形式、難易度の調整も可能です。これで学力アップに励んでいる中学生は結構多いんですよ。
※生成AIに作ってほしい内容を伝える「お願い」や「指示」を「プロンプト」といいます。
また、最新の生成AIにはボイス機能もあり、中学英語もスピーキングなどのオーラルコミュニケーションが占める割合が増えていますから、発音もテストできます。
——これは本当に「塾いらず」の賢い活用方法ですね!
田中:さらに、出来ないところがあっても生成AIは怒らないし、24時間いつでも丁寧に助けてくれますからね。有効な使い方はどんどん活用してほしいですね。
生成AIを利用することのデメリットとは?
一方、生成AIに対しては、「嘘をつくのではないか?」「個人情報の扱いは大丈夫なのか?」「人の考える力を弱めるのではないか?」といった批判的な意見もあります。こちらについても伺いました。
生成AIの「嘘」の正体とは?~ハルシネーション~
田中:まず、前提として生成AIに反対している人たちが言うほどの危機意識を持つ必要はないと私は考えています。そのうえで、よく出てくる生成AIに批判的な意見を見ていきましょう。
まずは、生成AIにはハルシネーション(事実に基づかない回答)が起きるという意見です。
——生成AIは嘘をつくのでは?ということですね。
田中:はい。ですがこれは、生成AIが「嘘をついて利用者をだましている」のではなくて、生成AIは「確率に基づいて回答をしている」だけなんです。例えば「明日の天気は?」と聞いたら、出てくる回答は「晴れ、曇り、雨、雪」になりますよね。
次に何%の確率でこの言葉が来るかと生成AIは計算しています。精度が高くなれば、ほぼ人間が考えるような状況を再現できます。ただ、確率ですので、時々間違えることがあるんです。
ここで、あることに関する生成AIの正答率が常に90%だったとしましょう。それが10回続いたら、0.9×0.9×0.9・・・・(0.9の10乗)で、正答率は0.3486784401、約35%まで下がります。
——半分以下になってしまいましたね。
田中:はい。これが生成AIのハルシネーションの実態です。長く複雑な問いかけになるほど、要素が増えるため、生成AIの正答率が下がっていってしまうんですね。
生成AIのハルシネーションは対策できる!
田中:生成AIもハルシネーションについては対策をしており、今の生成AIは「不確かな情報を用いて生成しない」というルールをすでに勉強しています。
さらに言えば、人間側が、ハルシネーションを防ぐように生成AIに伝えればいいんです。
生成AIに、「生成した情報や知識が不確かだ、という判断ができるなら<この情報は不確かです>とか、<私はこの分野については知識が不確かなのでお答えできません>と回答してください」と指示する。そうすれば生成AIも「その分野については知りません」と答えてくれます。
そのほかに「政府の発表、大学の発表など、専門的な知識を持つ機関の情報だけを参照して生成してください」と伝えてもいいですね。これは、ぜひ子どもたちにも教えたいですね。
——生成AIはそれらしく作ってくれるのが上手です。だからこそ「引用元」もしっかり伝えるというのは、大人であっても気を付けたいですね。
生成AIで個人情報が流出する?

——生成AIに入力した自分の個人情報をほかのシーンで勝手に使われてしまうのでは、という懸念もありますよね。
田中:「生成AIに入力した自分の個人情報が流用されてしまうことがないように」という学習も生成AI側で進んでいます。ですが、心配ならば、個人情報の入力は避けた方がいいでしょう。
一方で危惧されるのが「自分以外の他人が、自分の情報をネットに公開していた場合」です。
例えばスポーツ系の部活をやっている小中学生だと、そのスポーツのファンが善意のつもりで、勝手にその子の個人情報や大会の成績、顔写真などをアップしているケースがあり、それが生成AIによって学習されてしまうんです。
そのため、生成AIに子どもの名前を入力したら、詳細な情報が出てきてしまうということも考えられます。これは現時点で防ぎようがないかもしれません。
生成AIのせいで、子どもは考えなくなる?①新しいサービスは叩かれる
——生成AIに頼り切って、人が考えなくなってしまう、という批判もありますよね。
田中:はい、こういった批判は昔から繰り返しあります。私が子どものころの昭和40年代は、NHKの教育番組について反対運動があったんです。「テレビは情報が一方的に流されてくるから子どもの思考力が育たない。だから、見せてはいけない」と。
その後、昭和50年代後半くらいからは、学校にコンピュータが入ってきだしたのですが、このときも予想はつくと思いますが、また反対運動が起きました。
——新たなサービス、特に子どもに関するサービスは批判されがちですよね。
生成AIのせいで、子どもは考えなくなる?②生成AI利用のゴールデンルールとは
田中:ただ、確かに生成AIの利用によって、子どもが考えなくなってしまうという危惧はあるかと思います。
文部科学省が「学校現場における生成AIの利用について 」というガイドラインを発表しており、こちらがとても良いのですが、一つ肝心なところが抜けているんです。それは「初めは自分で考える」ということです。
あくまでも「初めは自分で考える」ことが大切なんですが、生成AI利用の実態としては、逆の場合が多いように思えますね。考えずにとりあえず生成AIに聞いてみようと。
——身に覚えがあるというか、そんな使い方ばかりしていました。
田中:もちろん「家族で旅行に行くのでプランを立ててください」といったものなら聞いてもよいのですが、学習、研究的な側面で最初から生成AIに聞くのは思考停止であり、危険です。
特に子どもは、これから思考力、創造力性を育てる時期ですから、「最初から生成AIに丸投げ」では、考えなくなってしまいますよね。
生成AIを利用していると、どんどん対話は膨らんでいくのですが、それは自分の思考力ではない、ということは理解しておきたいですね。生成AIが助けてくれているだけ、乗せられているだけなんです。
——耳が痛いです…。
田中:やはり「初めは自分で考える」ですね。「人間ファースト」です。これは生成AI利用のゴールデンルールだと思います。
生成AIを使うときに注意したい点
生成AI利用時に、気を付けないといけないことは何か考えていきます。
著作権に注意!学校と私的利用は「例外」であることを知らないと混乱も
田中:生成AI利用時は、著作権に注意しましょう。「有名なアニメキャラクターの○○君がこちらを振り向いているところを描いて!」と生成AIに出力してもらい、それをSNSに公開することは著作権法上、問題です。ただ、こういった形では画像が出せないよう生成AI側も学習しています。
そのほか、気を付けないといけないのが「著作権の例外」です。「学校での利用」と「私的利用」は著作権の例外になっています。そのため、子どもほど「学校ではいいのに、なんでほかの場所ではだめなの?」と混乱してしまうかもしれません。大人がきちんと説明する必要があります。
【参考】著作権の学びはこちらからも深められます:
https://anshin-game.jp/promise/report/250605.html
生成AI利用は「法律」だけでなく「モラル」も意識したい
田中:生成AI利用においては、先ほどお話したような著作権などの「法律」はもちろん守る必要があります。ただそれだけではなく、法律ではないものの、情報の倫理であったり、モラルであったり、適切に使おうというリテラシー(適切に使おうとする態度)も大切ですよね。
例えば、「今は学校の授業中で著作権の例外の時間だから何をしてもいいんだ!」と人の著作物をむやみやたらに使っていたら、法律では守られているけれど、リテラシーは育たないですよね。
生成AIデータを活用したいとき利用規約は必見。生成AIに要約してもらう手も

田中:生成AIで作ったデータを活用したい、ということも出てくると思いますが、そのような場合は、その生成AIサービスの利用規約を確認しましょう。どこまでを利用できるかなどが書いてあります。
——利用規約って、小さい字で書いてあって、海外発のサービスも多いですから翻訳された硬い日本語で読みにくいんですよね。
田中:そんな時は、利用規約を生成AIに要約してもらいましょう。 でも、時々「ここに書いてありますから、ご自身でお読みください」とURLを出してくることもあります。生成AIも冷たい時があるんですよ(笑)。
ただ、そういう時も、長くて読みにくいなと思ったら、「そんなこと言わないで要約して」とお願いすれば要約してくれますので。
——利用規約はつい読み飛ばしがちですから、ゲームなどスマホで新しいサービスを利用するときは、生成AIに利用規約を要約してもらうことを習慣にしたいですね!
生成AIが頼りになりすぎて、生成AIなしでは生きていけない?
田中:そのほか、生成AIの利用で気を付けたいことが、生成AIへの依存です。生成AIはマウントも取らず、時間に関係なく、いつでも優しく話を聞いてくれます。ですから、相談相手として生成AIを活用している人は若い方でも多くいます。
生成AIに相談することで、すっきりして現実に戻っていけるなら良い使い方であり、問題ありません。ですが、生成AIとの対話が快適すぎて、対人コミュニケーションを避ける子どもが出てきているのではないか、というのは気がかりな点です。もともとコミュニケーションが苦手な子どもが、それを乗り越えようとしないで、生成AIとの関係に依存してしまったりですね。
これは生成AIに限らず、スマホ依存やSNS依存でも同じことが言えますが、子どもがリアルの対人関係を避けるほど何かにのめりこんでしまっているのは、親が見たらわかるはずですから、注意したいですね。
あと、こちらは生成AIに限った話ではありませんが、生成AIを利用し、端末を見続けることでの視力低下や斜視といった目の問題は心配ですね。
【参考】スマホ利用において目の健康を考えたい方はこちらもどうぞ:
https://anshin-game.jp/promise/report/230530.html
生成AIは未来の必須ツール、生成AIと共に学び、成長するために
田中:ここまでお伝えしてきた点に気を付けながら、自制心、セルフコントロール力を持って生成AIを利用すれば、メリットの方が大きく、過度に生成AIを怖がる必要はありません。
人間の力には限界があります。生身の人間は100メートルを8秒で走れないですし、脳は今から倍の大きさにはなってくれません。
ですが、「生成AIに丸投げ」ではなく「最初は自分で考える」ことを大切にしていくことで、人間+生成AIでコラボレーションが進み、人間の能力も伸びていくのではないでしょうか。
- POINTまとめ
-
- 生成AIの「嘘」は指示の出し方を工夫すれば防げる!
- 「生成AI依存」「著作権違反」「生成AIに丸投げ」には注意!
- 生成AI利用のゴールデンルール:最初は自分で考える
 インタビュアー/ライター
インタビュアー/ライター
石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter(X)『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂