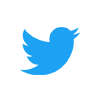子どもがスマホやゲームばかり!目が悪くなるわ!こんなん見てないで勉強しなさいッ
勉強はスマホより「目に良い」のかのう……?
- もくじ
- 平松類さんプロフィール

-
二本松眼科病院副院長、YouTube「眼科医平松類チャンネル」は登録者18万人以上、眼科医として唯一のYahooニュース公式コメンテーター。北米・ヨーロッパ・アジアをはじめ海外から診察に訪れる人がいる。書籍の累計発行部数70万部以上。 著書に「目まもりドリル」(ワニブックス)「子供ガボール」(主婦の友社)など
子どもが長時間デジタル機器を利用することによる視力低下を心配している親御さんも多いと思います。GIGAスクールも始まり、デジタル機器は勉強の道具でもあるので、取り上げるのも難しい状況ですよね。子どもとデジタル機器が切っても切れない今の時代において、視力低下を防ぎながらスマホやゲームと上手に付き合っていく方法を二本松眼科病院の眼科医、平松類先生に教えてもらいました。お子さんの視力低下が心配という保護者さんは、ぜひ参考にしてみてください。
デジタル機器により、子どもの視力低下は進んでいる?
スマホやゲーム機といったデジタル機器は、子どもの目にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。
スマホも勉強も、同じ理由で目に悪い
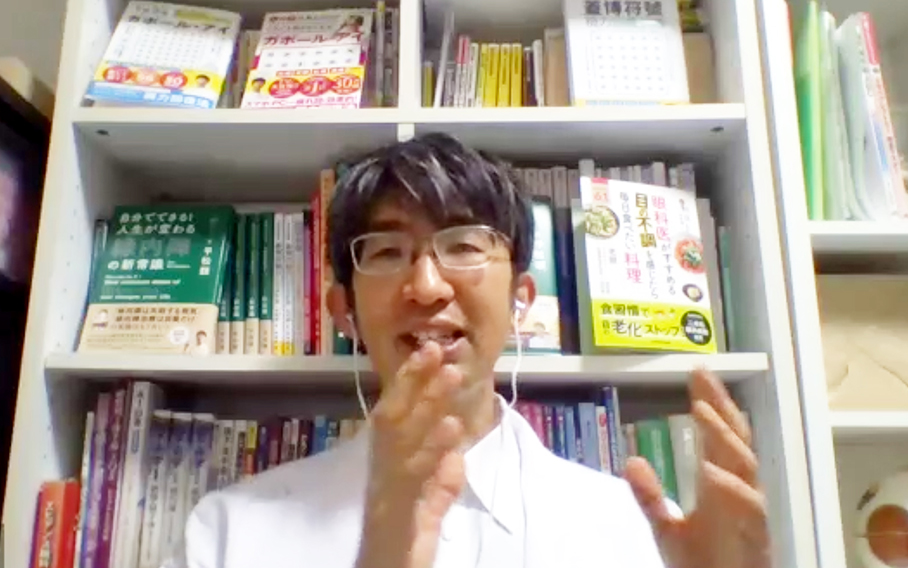
――スマホやゲーム機といったデジタル機器の利用により、子どもの目や視力に変化は起きているのでしょうか。
平松: スマホやゲーム機は悪役にされがちなのですが、スマホやゲーム機が悪いのではなく、「手元でものを見ること」が近視の進行に影響することが分かっています。ですので「スマホを見る」も「机で勉強する」も手元の作業であり、多少の差はありますが、実はともに目には良くありません。
――「勉強だって目に悪い」は衝撃的な事実ですね。
平松: はい。外来にお子さんを連れて来る親御さんは、眼科医である私から「目に悪いんだからスマホなんてやめて、勉強しなさい」と言ってくれるのを期待しているのだろうな、と思うことも多いのですが、医学的な見地から言えば「スマホ」も「机で勉強」も同じ理由で目に悪いです。なお、実感としては子どもの近視が一番進むのは、勉強する時間が増える受験の時です。
視力低下を食い止めているシンガポール、台湾
――スマホやゲーム機は日本に限らず世界中の子どもたちが夢中ですよね。スマホやゲーム機という手元での作業が増え、世界各国の子どもの目はどんどん悪くなっていそうですが……。
平松: 日本を含めて先進諸国で、子どもの近視は進んでいます。ですが、ちゃんとケアをすれば、近視の進行は止められることもわかっています。シンガポール、台湾では国を挙げて目の健康への啓蒙を積極的に行い、近視の進行が抑制されています。
視力低下を防止する方法①「デジタル機器と目の距離を離す」
手元の作業は目に悪いけれど、きちんとケアをすれば視力低下を防ぎ、目の健康をキープできる、ということで、家庭で今日から始められる、目のケアの具体的な方法を伺いました。
視力低下を防ぐにはモニターは大きいほど良い
――視力低下を防いで、目の健康を保つために、スマホやゲーム機などのデジタル機器を利用する際のポイントを教えてください。
平松: 2点あり、まず1点目は「デジタル機器と目の距離を離すこと」です。
――「スマホを目から離しなさい」とは、多くの親御さんが子どもに伝えていると思いますが、できている子どもは少ないですよね。
平松:
はい。スマホやゲーム機に集中しているときに、それを「離す」のって、そもそも難しいですよね。ですので、まず「モニターを大きくする」ことを意識しましょう。
スマホなら、モニターのサイズはより大きい方がいいし、スマホよりはタブレットがいいし、タブレットよりはリビングのテレビに接続して映した方がいいです。モニターが大きければ自然と目と端末の距離が離れますから、視力低下を抑える効果があります。
――「モニターを大きくする」はシンプルで分かりやすいですね。
平松: 特に、視力が低い子どもの場合「見ようとしてモニターに近づき、近視が進み、それでさらに見ようとモニターに近づき……」の悪循環になってしまうので、大きめのモニターを意識したいですね。
「スマホを目から離しなさい」は言った気になっているだけ?

平松: また「スマホを目から離しなさい」という曖昧な表現ではなく、「スマホを目から30センチは離しなさい」と、数値で伝えたいですね。なお、A4用紙の縦幅が大体30センチです(29.7センチ。ちなみに子どものノートでよく使われるB5の縦幅はそれよりも短い25.7センチ)。
――街中でスマホをしている人を見ても、A4用紙の縦幅の距離をキープできている人はそう多くない気がします。
平松: はい、スマホはつい20センチくらいに近づけて見がちなので、画面から目を離して視力低下に気を付けたいですね。A4用紙の縦幅、という目安があるだけでも違うと思います。「スマホを目から離しなさい」と言うだけでは、「言った気になっているだけ」とも言えますね。
視力低下を防止する方法②「30分に1回の休憩」
目の健康のためのポイントは「デジタル機器からの距離」が大切なことが分かりましたが、もう1点についても伺っていきます。
30分に1回は6メートル以上遠くを20秒ほど見よう
平松: 目の健康のために大切なことの2点目は「休憩」です。これも「たまに休憩を取りましょう」では曖昧ですので「30分に1回、6メートル以上遠くを20秒ほど見ましょう」と具体的に示すのが望ましいですね。30分に1回の休憩は、日本眼科医学会も推奨しています。きちんと休憩できるよう、タイマーを活用するといいでしょう。
――休憩時に、6メートル以上の遠くを見るのはなぜなのでしょうか。
平松: 目の玉の中には「水晶体」というレンズがあるのですが、人が手元を見るときは水晶体にくっついている「毛様体筋」が緊張します。毛様体筋が緊張したままだと、視力低下や近視が進行してしまうんですね。そこで定期的に休憩を取り、遠くを見ることで毛様体筋の緊張を和らげてあげることが狙いです。
「紙」と「液晶画面」を見ている時の違いとは?
スマホでも勉強でも手元の作業は目に悪いことが分かりましたが、ただ、ノートなど紙のものを見ているときより、スマホやゲーム機などの「液晶画面」を見ているときの方が、目が疲れる感覚になる人もいるかと思います。「紙」と「液晶画面」を見ているときの違いについても伺いました。
液晶画面は瞬きをする回数が減る
――「紙」と「液晶画面」を見ることにおいて違いはあるのでしょうか。
平松: 2点あって、まず液晶だとまばたきが少なくなる傾向があります。人間はボーっとしていると、1分間に20回ぐらいまばたきをしますが、紙を見ている時のまばたきは12回に、液晶を見ている時のまばたきは6~7回くらいまで減ってしまうとも言われています。ですので、液晶画面を見ている時は意識的に休みを取ることが大切ですね。
液晶画面を見ると、興奮する?
平松: 紙と液晶画面を見ることの違いの2点目ですが「目」への影響ではなく、自律神経への影響が考えられます。
――自律神経とは、自分の意志と関係なく動き続け、呼吸や体温調整、食べ物の消化などといった、生命維持に必要な活動をする神経ですよね。
平松: はい。そして自律神経は日中活動するときに働く交感神経と、夜間のリラックスしているときに働く副交感神経に分けられますが、液晶画面のように「光っているもの」を見ると、交感神経が刺激され、活動している時のような興奮状態になってしまうんですね。
――寝る前にスマホを見ていたら、眠りたいのに目が冴えていってしまう事って確かにありますね。これも「興奮状態」なのですね。
平松: はい。ですので、液晶画面の輝度(明るさ)をあまり上げすぎない、明るくし過ぎないことも重要です。明るい方が見栄えが良いですから、初期設定の輝度は高すぎることもあります。輝度はどの程度が適正かという数値はないのですが、まぶしすぎない適度な明るさを意識してみてください。
スマホやゲーム機は「悪者」ではなく、使い方が大切!
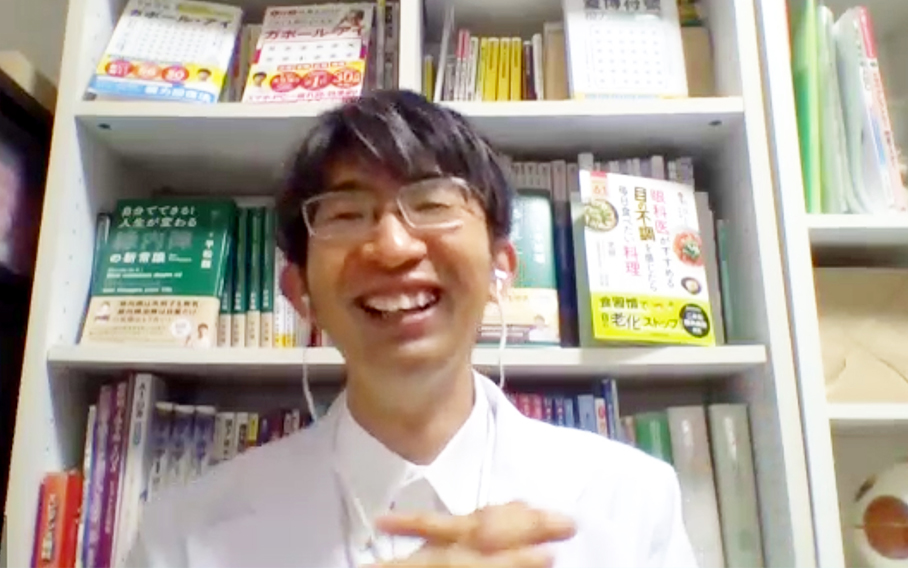
――大切な目の健康のために、毎日の生活でできることがよく分かりました。最後に、お約束メイカーの感想について教えてください。
平松:
ゲーム会社さんが画期的なことをされているな、というのが率直な感想です。
スマホやゲーム機は「悪役」になりがちですが、本日お話したように使い方の問題なんですよね。「スマホやゲーム機を取り上げるかやらせるか」の2択ではなく、「デジタル機器と30センチは距離を取ろう」といったところが、現代の現実的な着地点かと思います。
「スマホは30センチ以上離す」「30分に1回は休憩を取り、6メートル先を見る」など、数字をはっきりさせた約束をお約束メイカーで結んでも良いですね。
- POINTまとめ
-
- スマホも勉強も「手元の作業」なので目には悪い!
- 視力低下を防ぐにはモニターを大きくし、「端末から30センチ以上」離れる習慣を
- 30分に1回、6メートル先を見て目を休ませよう
 インタビュアー/ライター
インタビュアー/ライター
石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂