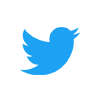子どもにSNSなんて、トラブルしか起こさないわ!禁止禁止禁止ッ!
子どもが親に隠れて使ってしまうことを一番避けなくてはいけないのジャ!
- もくじ
- 高橋暁子さん

-
ITジャーナリスト。成蹊大学客員教授。SNSや情報リテラシー教育が専門。SNSや情報リテラシーに関する書籍を多数上梓する他、全国の小中高校大学、自治体、団体、企業などを対象に毎年 50回ほどの講演・セミナーも開催。NHK『あさイチ』『クローズアップ現代+』などメディア出演多数。『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』(講談社+α新書)等著作多数。教育出版中学2年生の国語の教科書にコラム掲載中。
ホームページ https://www.akiakatsuki.com/
X https://x.com/akiakatsuki
小学生からスマホを持ち始める子ども達が増えているなかで、多くの保護者や教員が心配になるのがSNSの利用です。今回は、そんなSNSの最新情報からトラブル事例まで、SNS時代の子ども達を取り巻く状況について、ITジャーナリスト・成蹊大学客員教授の高橋暁子さんにお話を伺いました。
子どもとSNS、保護者が必要な心構え
子どものスマホ利用と切っても切れない関係のSNSですが、保護者はどのような心構えでいればいいのでしょうか?
SNSは「友人関係そのもの」。禁止は難しい
高橋:スマホを利用する子どもにとって、SNSは本当に大切で必要なものです。SNSは友人関係そのものなので、「禁止」、「使わない」は無理で、そこは分かってあげていただきたいですね。
ペアレンタルコントロールを利用したり、各SNSの子ども向け機能制限を利用したりする方法もありますが、残念ながら一部の機能には抜け道もあります。そのため、機能だけに頼らず、保護者と子どもとの間で「こういった利用はしてほしくない」ということについて話し合い、納得、合意することが大切です。
SNSで共通するリスクとは?~そもそも小学生向けのサービスではない~
——今回の記事では子ども世代にも人気のSNSである、LINE、Instagram、X、TikTok、YouTubeのリスクや魅力についてお伺いしたいのですが、まず、個別のSNSについてお話を伺う前に、これらSNSで共通するリスク、魅力について教えてください。
高橋:SNSに共通するリスクは、ネットいじめや知らない人と出会ってしまうこと、そのほか、長時間利用やデマも多く、誤った情報を信じてしまったり、拡散してしまうことです。
なお、各サービスの利用規約上の年齢制限は以下の通りです。(2025年7月時点)
|
LINE |
Instagram |
X |
TikTok |
YouTube |
| 12歳以上推奨 | 13歳以上 | 13歳以上 | 13歳以上 | 13歳以上 |
——公式が「13歳以上(LINEのみ12歳以上)」と規約上に記載しているのは、「それ以下の年齢では使いこなせない」「使うと特にトラブルになりがち」という側面があるのでしょうね。特に小学生に使わせる場合は「ほぼ小学生を対象にしていない」サービスを使わせている、という意識は保護者側に必要ですね。
「子どもとSNS」は悪いことばかりではない
高橋:次に、SNSに共通する魅力ですが、「知らない人と新たに出会う」ことをポジティブに捉えることもできます。例えば子どもが学校でいじめられていたりなど、居場所がない場合、SNSが自分の居場所になる、セーフティネットになる可能性があります。
保護者もうれしい!勉強へのSNS活用

高橋:また、勉強にSNSを活用しているケースもあります。SNSで「勉強垢(勉強アカウント)」を高校生ぐらいになると作る人も増えてきます。
「今日は○時間勉強した/○○大学に入るぞ/偏差値いくつ上げるぞ」などを話題としたアカウントですね。こういったことは学校の友達には言いづらいですよね。
——「SNSの匿名性」というと悪い活用法が浮かびがちですが、勉強垢はいい意味で匿名性を活かしていますね。
高橋:またLINEなどのビデオ通話機能を活用し、友達とビデオ通話状態にして、その時間は会話をせず、他のことをせず、お互い勉強しよう、という使い方もあります。これは素晴らしい使い方ですよね。
LINE、Instagram、X、TikTok、YouTube、子どもはどう使っている?
続いて、大人にも人気な5つのSNSについて特徴を伺いました。子ども達は、大人には思いもよらない使い方もしているようです。
LINE①子どもはLINEを「出会う」ツールとして使う
——次に個別のSNSについて、子ども達の利用実態や、魅力やリスクについてみていければと思いますが、まずLINEはいかがでしょうか。
高橋:ニフティキッズさんの2024年の調査を見ると、小中学生の約7割にネッ友(ネット上の友達)がいるんですね。ネッ友と何で知り合ったかも調査されているのですが、1位がオンラインゲームで、次がLINEのオープンチャットなんです。
参考:ニフティキッズ 子どものホンネ 調査レポート
小中学生の約7割は「ネッ友」がいる。“リアルな友だちよりもネッ友の方が居心地がいい”中学生の理由は「素の自分が出せる」
https://kids.nifty.com/parent/research/nettomo_20240801/
LINEは、大人にとっては知り合いと連絡を取る手段ですが、子どもにとっては新しい人と出会うために使われてるんですね。
LINE②これがなくては学校生活が送れないインフラ
高橋:LINEのリスクとしては、他のSNSよりも外からやりとりが見えづらく、ネットいじめが起きやすく、トラブルが起きても見つけにくいという点があります。
ですが、LINEは日本ではもうすでにインフラになっています。特に中学生になると、スマホを持ってない子でもLINEがないと連絡上困るということで、パソコン上にアカウントを作ったり、親のスマホを借りてLINEを使っているケースもありますね。
「部活の練習時間が変わります」「この申し込みは明日までです」などの急ぎの連絡がLINEでされているんです。今、学校には「連絡網」がありませんので、その代わりに「LINE教えてよ」という感じですね。必須中の必須になっていますね。
Instagram~コンプレックスを刺激する「映え」~
高橋:次にInstagramですが、固有のリスクで言うといわゆる「映え」によるコンプレックスの刺激ですね。
インスタで多くの「いいね」をもらう人たちは、ムダ毛もなくスタイル抜群で美しい方たちなのですが、画像を加工していて、実際の姿ではないことも多いです。ですがそういった人たちを毎日見ているうちに実際の姿だと思い込み、自分はそれに比べて……となってしまうのは問題ですね。これは日本に限らず海外でも問題になっています。
X~情報収集、速報性は強いが、誹謗中傷も多い~
高橋:Xは情報収集にはとても便利ですよね。リアルタイムで起きたこと、例えばテレビ番組の感想をリアルタイムで共有したり、最新のニュースをチェックしたりなど、速報性は非常に優れています。
ただ、言葉でやり取りするSNSなので、言葉尻をとられての言い合いや中傷も多いです。年齢が低いうちは、情報発信はせずに、情報収集中心で使った方がいいかもしれません。
TikTok①「承認されやすさ」が魅力でもありリスク

高橋:TikTokは今回紹介している他のどのSNSよりも発信者の承認欲求を満たしやすいのが魅力でもあり、リスクでもあります。
子どもには、自分で発信して人の目を引くようなコンテンツなんてなかなかないわけです。ですが、TikTokなら子どもが自撮りして投稿するだけで「可愛い」「いいね」と褒められるからそれが嬉しい、という娯楽的な喜びはあると思います。
TikTok②死者も出ている「チャレンジ動画」
高橋:TikTokの固有のリスクとしては「チャレンジ動画」があります。「失神チャレンジ」など、あえて危険なことにチャレンジする動画で、過去のチャレンジ動画では亡くなった人もいます。
危険なチャレンジ動画はYouTubeにもありましたが、YouTubeはほとんど運営側に削除され、チャレンジ動画では収益化できないようにするなど対策も取られています。しかし、TikTokではYouTubeに比べて対策が十分でない傾向はあります。
YouTube①高額投げ銭(スパチャ)に要注意!
高橋:最後にYouTubeですが、YouTubeならではのリスクとしてスパチャ(スーパーチャット、YouTubeにおける投げ銭)問題があります。投げ銭はTikTokやInstagramにもありますが、YouTubeの投げ銭であるスパチャは金額が大きくなりがちです。
スパチャは、実際の現金を出さずスマホをポチポチ操作するだけですから、子ども達にとって払っている実感が乏しいのも問題です。それが親のキャリア決済になっていたら、ますます子ども側は払っている感覚を持ちにくいでしょう。
多額のスパチャをしたユーザーは画面上で目立って長く表示されるので、配信者から名前を呼んでもらったり、お礼を言われたり、リクエストを聞いてもらえたりするので、「もっともっと!」となるようにできているんですね。
YouTube②スパチャ対策は複数の方法で、こまやかに!
高橋:スパチャについては、ご家庭の方針として子どものスパチャを許可するか、しないかをまず決めましょう。スパチャをOKとした場合も、金額の上限は必ず決め、子どもが簡単に課金できる設定にしないことも重要です。
主な課金対策としては以下の通りで、これはスパチャに限らず他の課金でも同様です。
- ・課金の際のパスワードを設け、都度保護者がパスワードを入力する
- ・スマホとクレジットカードを紐づけておかない。紐づける場合は利用ごとに明細がメールなどで届くようにし、すぐ確認する
- ・キャリア決済は上限を設定しておき、上限を超えるとアラートが保護者に届く設定にするだけでなく、そもそも上限金額以上は利用できない設定にする
——何か一つやればいいというわけではなく、複合的な対策がいるのですね。
高橋:そうですね。大人なら課金に対し「これ以上はできない」という自制心が働きますが、小中学生にはそういった加減や程度がまだ分かりません。そんな子どもに対し、大人同様に「自分の責任で自由に使っていいよ」とスマホを与えたら、子どもは好き勝手に使ってしまいます。
これは、子どもが悪いわけでも、サービスの提供会社が悪いわけでもありません。スマホを子どもに渡す以上、保護者がしっかり管理なさらないといけませんよ、というお話です。
ペアレンタルコントロールは破られるので意味がない?は大間違い!
親子の約束とペアレンタルコントロールを活用し、子どものSNS環境を安心・安全にしていくための対策について教えてもらいました。
ティーンアカウントもあるのだが…
——SNSによっては、子ども向けに機能を制限したアカウントを提供しているケースもありますよね。
高橋:そうですね。Instagramにはティーンアカウント、TikTokはペアレンタルコントロールがあり、これらを使うと、問題のある動画を表示させなくさせたり、知らない人との接触を防いだりすることができます。
ですが、その中には子ども側の端末で設定するものもあり、子ども自身であとからいくらでも設定をもとに戻せてしまうものもあるんですよね。ですので、親子で話し合いの上、双方が納得、同意していることが大切です。
ペアレンタルコントロールなんて意味がない?という大きな誤解
——抜け道もあるので、「ペアレンタルコントロールなんて意味がない」と、設定しない保護者もいますよね。
高橋:抜け道も一部はあるのですが、ペアレンタルコントロールで防げることもとても多いです。ペアレンタルコントロールは無料で利用できるものも多く、主要なトラブルはカバーされています。
そもそも、スマホトラブルについて、保護者側が何も知らず、調べず、全く対策しないで子どもにスマホを自由に使わせたら、大体トラブルになります。
トラブル発生後「大変なことになった」と相談に来られる方もいらっしゃるのですが、ペアレンタルコントロールソフトや、アプリ側で用意されていた対策を入れていれば、防げたケースも多いんです。
長時間利用や課金はペアレンタルコントロールである程度防げますし、ペアレンタルコントロールをしていること自体が抑止効果にもなるわけですから、活用しない手はありません。
親子の話し合いのコツは「事例を紹介」「心配だから」

——子どもとスマホの利用について話し合う際は、どういった点に気を付けるといいでしょうか。
高橋:実際のニュースを切り口にして話し合うと、子どもにもイメージがしやすいかもしれません。「この事件のように、子どもが性被害にあったり、殺されたりするケースもある、あなたが心配だからこういう風にしたいけど、どう思う?」と尋ねましょう。
参考:インターネット、スマートフォントラブル相談窓口『こたエール』サイト内 子ども関連記事。子どもが被害に遭った事件のリンクが紹介されています
https://www.tokyohelpdesk.metro.tokyo.lg.jp/data/
親子の約束を子どもに破られたらどうする?
——約束を子ども側に破られるケースもありますよね。
高橋:はい。「知らない人とやりとりをしてはダメ!」と約束していても、やりとりしてしまっていたとか。親子で結んだペアレンタルコントロールの設定を子どもが勝手に変えていたりとか。
ただ、子どもは約束を破ったことで怒られたり、それによってスマホを取り上げられたりすることを恐れますから、隠れてなんとかしようとしてトラブルが大きくなることがあります。これは一番避けなくてはいけません。
ですので、「スマホで困ったことがあったら味方をするから、隠さずすぐに相談してね」とスマホを渡すときに伝えたいですね。
ネッ友に会っている小中学生は16%という調査結果も
——子どもが「ネッ友とどうしても会いたい!」というのも保護者にしてみれば悩ましいケースですね。
高橋:もちろん、「会わない」に越したことはないのですが、「親に言ったところで反対されるからこっそり会う」のが1番ダメなんですよね。先ほどのニフティキッズさんの調査でも、小中学生の約16%がネッ友に実際に会ったと回答しています。
——少なくない数ですね。
高橋:はい。ですので、「会うのだったら必ず保護者に相談してね」も選択肢かもしれません。性別や年代を偽り、子どもと同性、同世代だと装って近づく人もいます。会う前にビデオ通話をして性別や年代に偽りがないか、会っていい人か確認しましょう。
そして会うならば、いつどこで誰と会うかを必ず保護者に言うこと、会う場所は日中、公共の場所、もしくは人の多い場所をこちらが指定して、決して2人きりにならないことです。現地まで保護者が送り迎えをする、でもいいですね。
ネッ友は「ゲームつながり」が多いです。今のゲームは話しながらプレイしますから、子どもにしてみれば、もう親友みたいな感覚なので会いたいのでしょうけれど、残念ながら悪い人もいますから。
インターネットに詳しくなくても、保護者にできることはある!
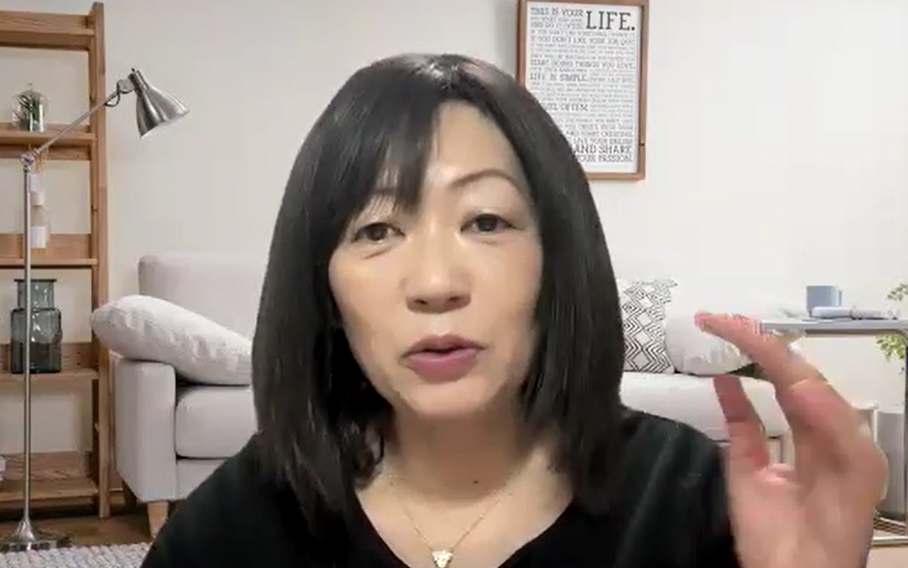
——保護者の中にはSNSをあまり使わないのでよくわからない、という方もいると思います。どう子どもをサポートしていけばいいでしょうか。
高橋:トラブル時の相談機関は前もって把握しておきたいですね。自治体、都道府県には保護者、子ども双方に向けた相談窓口が開設されています。
それらを踏まえ、子どもには「ネットは詳しくないけれど、困ったときに誰に、どこに相談すればいいかはわかるから、困ったときは味方になるから相談してね」と日ごろから伝えておきたいですね。
※主要なネットトラブル相談窓口はこちらの記事で紹介しています。
- POINTまとめ
-
- フィルタリングと親子のルールの両輪でのSNS対策を
- 怒られることを警戒しトラブルを「隠される」ことがないように
- 実際のSNSトラブルの事件について、親子で話し合おう
 インタビュアー/ライター
インタビュアー/ライター
石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter(X)『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂