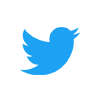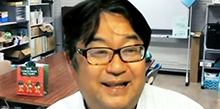ゲームは小学生の子どもの成長に悪い影響があるってよく言われるけど本当かな?
そんなことはないぞい! ゲームをするメリットもたくさんあるのじゃ!
- もくじ
- 山中智省さん

-
目白大学人間学部子ども学科専任講師。専門は日本近現代文学、サブカルチャー研究。近年は、日本の若年層向けエンターテインメント小説の一つである「ライトノベル」に着目し、その誕生・発展過程を探る研究に取り組んでいる。著書に『ライトノベル史入門 『ドラゴンマガジン』創刊物語―狼煙を上げた先駆者たち』(勉誠出版)、共編著に『小説の生存戦略―ライトノベル・メディア・ジェンダー』(青弓社)、共著に『メディア・コンテンツ・スタディーズ―分析・考察・創造のための方法論』(ナカニシヤ出版)などがある。
ゲームが小学生の子どもに与える悪影響はよく耳にするけど…
ゲームを禁止にしたことで、小学生の子どもが心を閉ざしてしまい、家族のコミュニケーションがうまくいかなくなったというケースも少なくないのではないでしょうか。現在、子どもたちにとってゲームは、なくてはならない存在となっています。ゲームのデメリットにだけ耳を傾けるのを止めて、ゲームのメリットについても知る必要があるのではないでしょうか。今回は、子育てや教育に関わるメディアとサブカルチャーを専門とする目白大学人間学部子ども学科専任講師の山中智省さんに話を伺いました。
子どもがゲームをすることによって得られる成長のメリットとは?
ゲームは小学生の子どもたちの想像力を高めてくれる

――ゲームが小学生の子どもの成長に与えるメリットはどんなものでしょうか。
山中: ロールプレイングゲーム(以下RPG)のような物語性の強いゲームは、子どもの想像力を高めてくれます。マンガやライトノベル、アニメなどにも同様の効果はありますが、ゲームならではのメリットは、子どもがキャラクターを操作して物語に介入できるところにあります。物語の中でキャラクターにどんな行動をさせ、どんな結果になるかを想像する要素や、自分とキャラクターを重ね合わせて得られる没入感はゲームでしか得られないメリットですね。
禁止にするよりも、ゲームをするメリットを活かせるような約束作りが大切
――“没入感”に関しては、批判の対象になることもありますよね。
山中:
「どうすればその世界に入り込んでもらえるか」を追求してRPGは作られているので、子どもが没入するのは当たり前です。その上、ゲーム内の操作に対してすぐに反応が返ってくるので、受動的に受け取るマンガやアニメと比べたら、確かに刺激の強いものと言えるでしょう。
だからこそ、ゲームを長時間続けてしまったり、より強い刺激を求めて高額課金をしてしまったり、といったトラブルにつながりやすいデメリットもあります。
しかし、ゲームは今や子どもたちのコミュニケーションツールとして、なくてはならないものです。単純に禁止するのではなく、日々の子育ての中で、親子でしっかり話し合って約束を作り、むしろゲームが持つ「子どもの想像力を高めてくれる」というメリットを最大限に活かすことこそ大切ではないでしょうか。
ゲームのジャンルによって伸ばせる能力が違う!
主人公を操作して、物語の世界に介入できるRPGを例に、ゲームをするメリットを語ってくださった山中さん。他のジャンルのゲームについても伺いました。
ゲームで「学ぶ習慣」を身につけられる
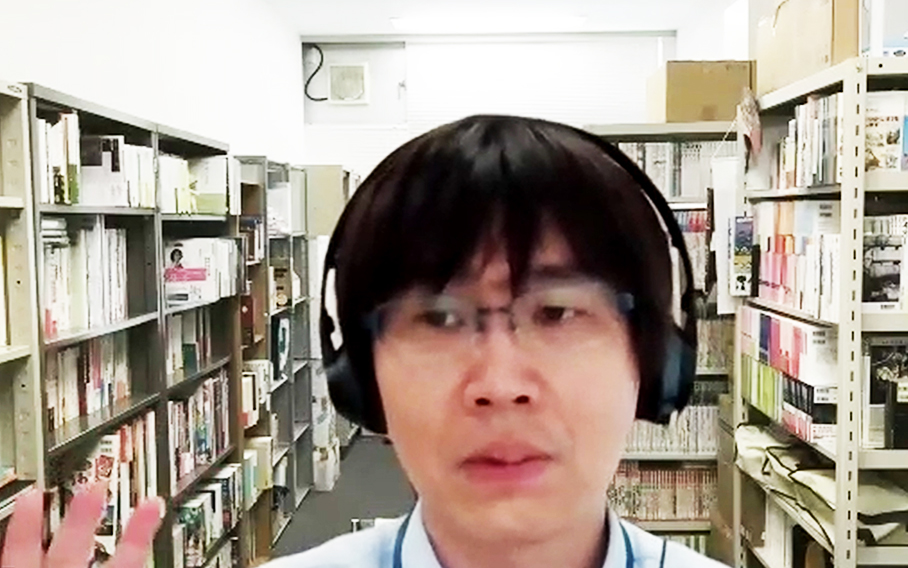
――RPG以外のジャンルのゲームについては、どのようなメリットがあるとお考えでしょうか。
山中: 歴史を題材にしたゲームは、子どもたちが歴史に興味を持つきっかけになりますよね。最近では、文豪や刀剣をキャラクター化したゲームなどもありますが、これらのゲームのメリットは、教養を深める入り口にもなっている点です。子どもに「勉強しなさい!」と強要しても、拒絶されるだけでデメリットしかないと思いますが、遊んでいるゲームを通じて「このキャラクターについて一緒に調べてみようよ」と子どもに話しかけてあげることで、子どもが「学ぶ習慣」を身につけることができるようにもなります。
オンラインゲームは、子どもの協調性を育んでくれる
――そのほか、教育に活用できるようなゲームにはどのような要素がありますか?
山中: 例えば、ブロックを使って道具や建物を作る『Minecraft』 (マインクラフト)は教育現場でも活用されています。オンラインでつながった共通の世界で、ほかの子どもたちと一緒に道具や建物を作ったり、冒険したりすることによって、協調性を育むことができます。
――『Minecraft』のようなオンラインゲームは子どもたちの間で人気ですよね。
山中: そうですね。親御さんの中には、オンラインでの交流ではなく直接対面でのコミュニケーションを重視する方もおられ、オンラインゲームのメリットを見いだせない方もいるかもしれません。しかし、現代はSNSがこれだけ普及していますから、インターネット上でのコミュニケーション能力も重要になっており、社会で生きていく上では、欠かせないスキルになりつつあります。特にコロナ禍の現状においては、オンラインゲームが子どもたちにとって、重要なコミュニケーションツールであると同時に、コミュニケーション能力を育てる「学びの場」にもなっています。子どもたちには対面と同様にオンラインでのコミュニケーションが重要なもの、と理解して双方の機会を与えていただきたいと思います。
ゲームのデメリットや悪影響に対してはどうすればいい?
ゲームの様々なメリットについて理解できましたが、それでも依存をはじめとするデメリットについての不安は残ります。そんな不安に対して、子育て中の親は何をすれば良いのか具体的なアドバイスをいただきました。
ゲームと横並びになる多様な娯楽を提供することの重要性
――依存を含むゲームのデメリットに対して、子育て中の親はどう対処すれば良いのでしょうか?
山中: まずは、ゲームについての理解を深めることです。先ほど話したように、ゲームには教育的なメリットも多く存在します。漠然とした不安を抱くのは、ゲームを「よくわからないもの」として捉えていることが原因です。絵本や子ども向けアニメの場合、子どもにどんなコンテンツを見せるかを親がしっかりと選択できます。しかし、ゲームに関しては、詳しくないとその判断が難しい場合もありますよね。ゲームに詳しくない親御さんは、自身の印象や経験に基づいて、詳細を吟味せずにゲームを評価しがちで、急に否定したりすることがあります。一方的にゲームを否定されると子どもは頑なになり、親とのコミュニケーションを拒絶することも考えられます。
――一方的にゲームを禁止したことで、親子のコミュニケーションが上手く行かなくなってしまったご家庭もあるようですね。
山中: 子育てをするなかで、子どもがなぜゲームばかりしてしまうのか、なぜそのゲームに熱中しているのか、子どもの素直な言い分を、ぜひ聞いてあげてください。子どもの言い分に納得できない部分もあるかもしれませんが、まずは否定せずに受け入れる姿勢が重要です。それから「どうしてそう思うの?」「こうした方が良いんじゃない?」といった具合に、丁寧なコミュニケーションを通じて子どもの意見を理解しましょう。その上で、ゲームへの依存が強い子どもには、ほかの楽しみを体験する機会を少しずつ提供することも大切です。親がゲームの楽しさを理解した上で、本を買ってあげたり、アニメを一緒に見たり、どこかに出かけたりするのも良いかもしれません。また、クラブ活動や習い事を通じて、様々な横並びで楽しめる娯楽を子どもに提供することが大切です。これにより、ゲームだけに依存してしまうという状態から脱することができるのではないでしょうか。
ゲームが子どもの成長に与えるメリットを最大限活かすには
ゲームに関する会話が子どもの考える力や理解力を高める
――ゲームが子どもに与えるメリットを最大限に活かすために、親ができることを教えてください。
山中: ゲームに抵抗がない親御さんであれば、子どもと一緒にゲームをプレイするのが一番です。一緒に遊ぶのが難しい場合は、ゲームに関して子どもに話を聞いてみるのも良い選択でしょう。子どもとゲームについて話す中で「どんなところが楽しいの?」、「どうしてそう思ったの?」などと聞いてあげると、子どもがあらためてゲームのストーリーだったり、自分がゲームに対して抱いた感情だったりを考える機会になります。ゲームについて話すことは、子どもの考える力や理解力を養う一助にもなると思います。
――若い親御さんの中には、ゲームが好きな方も多いと思いますが、親が好きなゲームを子どもに勧めることについてはいかがでしょうか?
山中: 子どもは基本的に自分の手の届く範囲でしか世界を知りません。親が自分の経験を元に、好きなゲームを勧めることによって、子どもの世界を広げてあげるのはとても良いことです。ただし、親の価値観を子どもに押しつけたり、対象年齢が合わないゲームを勧めるようなことがないよう、気を遣う必要はあります。親にとっては素晴らしいゲームであっても、そのゲームが子どもにとってもメリットがある良いゲームとは限りません。ゲームを通じたメリットを最大限に活かすためにも、子どもの価値観や成長・発達の様子も大切にしてあげてください。
ゲームのメリットを活かす親子の約束作り
最後に、子どものスマホ・ゲームのトラブルを減少させるために、ガンホーが無料で提供している『親子でスマホとゲームのお約束メイカー』を山中さんに体験していただきました。
『お約束メイカー』は教育の現場を目指す学生にとっても貴重なツールです

山中:
ゲームが持つメリットを存分に活かすためにも、ゲームをする際の悪い影響をできるだけ少なくするための約束作りが大切です。『お約束メイカー』は、親子でコミュニケーションを図りながら、ゲームをするメリットを活かして約束を作ることができるので、ぜひ多くの親御さんに活用して欲しいですね。
私の場合は、保育者を目指す学生を指導する立場にありますので、ゲーム関連の啓発ツールがあることは非常にありがたいです。私のゼミにも子どもとゲームの関係を研究している学生がおりますので、早速、『お約束メイカー』を紹介させていだたきました。
こういった啓発ツールや情報サイトを通じて、教育の現場を目指す学生たちが、ゲームのメリットについて考える機会や知識を得られることはとても有意義ですし、今後の講義でも活用したいですね。
- POINTまとめ
-
- ゲームは子どもの想像力を高めるメリットがある
- ゲームを禁止するよりも、ゲームをするメリットを活かす約束作りが重要
- ゲームを通じて学ぶ習慣が身につく
- オンラインゲームは、ほかの人との協調性を養うメリットをもつ
- 子どもにゲーム以外の娯楽も提供してあげよう
- ゲームに関する会話が考える力を養う手助けになる
 インタビュアー/ライター
インタビュアー/ライター
斎藤 ゆうすけ- さいとう ゆうすけ。ライター・放送作家。大学在学中よりゲームメディアで記事の執筆を行い、現在はテレビやラジオの放送作家として活動。バンタンゲームアカデミーおよび東放学園映画専門学校にて、講師としてゲーム関連の講義も担当しており、バンタンゲームアカデミー高等部eスポーツ専攻ではプロゲーマーを目指す高校生向けにネットリテラシーの講義も行う。活動に関する告知はTwitter『斎藤ゆうすけ(アニゲウォッチャー)』にて発信中。