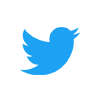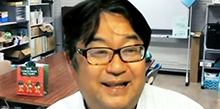小学生のゲームに関する課金トラブルが増えているみたいだけど、どうしたらいいのかなぁ?
スマホやゲームがあまり得意じゃない親ができる対処方法について聞いてきたぞい!
- もくじ
- 高橋暁子さん

- ITジャーナリスト。成蹊大学客員教授。SNSや情報リテラシー教育が専門。SNSや情報リテラシーに関する書籍を多数上梓する他、テレビ、雑誌、新聞、ラジオ等のメディア出演、全国の小中高校大学、自治体、団体、企業などを対象に毎年 50回ほどの講演・セミナーも開催。教育出版中学2年生の国語の教科書にコラム掲載中。令和2年より「青少年を取り巻く有害環境対策の推進」技術審査委員会技術審査専門員(文部科学省より委託)等、省庁からの依頼も多い。ホームページ / X
小学生の課金トラブルの実態は? 親ができる対処方法を知りたい!
小学生の子どもが「ゲームに課金したい」と言ってきた時、ゲームを全くやらない親でしたら、どうしたらいいかわからなくなりますよね?
小学生の子どものゲーム課金のトラブルや親が知っておくべきこと、そして課金トラブルがおきてしまった時に対処する方法についてITジャーナリスト・成蹊大学客員教授、高橋暁子さんにお話しを伺いました。
小学生のゲーム課金のトラブルって増えているの?
講演会や書籍の執筆、メディアへの出演などを通してゲームの課金に関するトラブルについて啓蒙活動を続けられている高橋さんにまずは、ゲームの課金トラブルの実態を教えていただきました。
コロナ禍でゲーム課金トラブルは増加の一途を辿っています
――ゲームの課金トラブルに関するニュースをしばしば目にしますが、実際、課金トラブルは増えているのでしょうか?
高橋:
コロナ禍で子どもが家でゲームを遊ぶ時間が増えたことで、課金に関するトラブルも増加しています。
国民生活センターによるとゲームの課金に関する相談は、コロナ禍で大幅に増加しており、2020年は小学生の子を持つ親御さんからの相談が前年比で約1.6倍、中学生の子を持つ親御さんからの相談が前年比で約1.3倍と、増加の一途を辿っています。
パソコンやタブレットに触れる機会が増えて課金が身近なものに
――親が子どもにゲームの課金やゲームそのものを禁止しているご家庭もあるかと思いますが、そういったご家庭でも課金トラブルは発生するのでしょうか?
高橋:
多くの親御さんが子ども達のゲームを制限していた家庭でも、学校に行けない時間や、友達と気軽に遊べない期間が続くと、「かわいそうだから」という理由で制限を緩めてしまうことが、結果的に小学生の課金トラブルの増加につながっている例も少なくありません。
さらに、2020年に開始された『GIGAスクール構想』によって、小学生や中学生一人ひとりにパソコンやタブレットが提供されることとなりました。このことにより、子ども達にとってパソコンやタブレットがますます身近なものとなり、こうした環境が子どもの課金トラブルの要因ともなっています。
学校では課金トラブルに関する指導がしっかりと行われ、ネットリテラシーの専門家を招いた講演も開催されています。しかし、子どもがゲームに課金したいという想いは強いため、課金トラブルを未然に防ぐためには、親御さんがゲームについてよく理解し、子どもとのコミュニケーションをしっかり取ることが不可欠となります。
子どもの課金トラブルの実例
コロナによって小学生の子どもが家にいる時間が増え、『GIGAスクール構想』でパソコンやタブレットが身近になったことで、課金トラブルの増加が見られる中、実例としてどのようなトラブルが起きているか高橋さんに伺いました。
実例① 子どもが親のスマホで遊んでいるうちに課金していた

高橋:
未就学児童(幼稚園児・保育園児)や小学校低学年の子どもがいる家庭では、親御さんのスマホでゲームを遊んでいるうちに、知らないうちに課金していたケースが挙げられます。ゲームにログインしたままのスマホを親御さんが放置していて、スマホで子どもが遊んでいるうちに課金されていたというケースもあります。このような場合、子どもが意図して高額な課金を行ったわけではないため、親御さんがスマホの管理を徹底していなかったことが問題となります。
共有のゲーム機や契約の切れた中古のスマホ、タブレットでも、クレジットカードを紐付けたアカウントからは必ずログアウトしてください。そうしないと、子どもによる課金トラブルを防ぐことができませんので、注意が必要です。
実例② 親のクレジットカードやキャリア決済で課金していた
高橋:
一方で、小学校中高学年の子どもや中高生になると、親のクレジットカードを無断で使って課金したり、携帯電話会社のキャリア決済を利用して、こっそり課金するケースがあります。親のクレジットカードが使われる場合、多くは親御さんがクレジットカードを子どもの目に見える場所に放置していたり、パスワードが子どもにも推測できるようなものだったりと、カードの管理に甘さがあります。
また、スマホを持ち始める小学校高学年頃から、子どもが携帯電話会社のキャリア決済を勝手に利用する課金トラブルも多く見受けられます。
親御さんはクレジットカードや子どものキャリア決済の明細をしっかり確認し、子どもの課金を早期に察知できるようにすることが重要です。
子どもの課金トラブルを防ぐために! 親がすべきことは?
小学生の子どもが関与する課金トラブルの実例について伺う中で、高橋さんは「親がスマホそのものやクレジットカードの管理を徹底することが大事」と強調されます。
クレジットカードの管理を徹底し、明細は必ず確認しましょう
――どうすれば小学生を含む子どもの課金トラブルを防ぐことができるのでしょうか?
高橋:
まずは親御さんが自分のスマホやクレジットカードの管理をしっかりと行うことが重要です。
私自身、ゲームを実際に遊んでみると、課金をすることでキャラクターが強くなったり、見た目を変えられるなど、ゲームの進行が円滑になることがあります。課金をしたくなるポイントが多く、小学生の子どもたちもたくさんの友だちが課金しているため、「ゲームに課金したい」と思うのは当然のことです。この気持ちを頭ごなしに否定するのではなく、まずはしっかりと理解した上で、子どもが勝手に課金しないように対策を取ることが大切です。具体的な対策としては、
・クレジットカードのパスワードを子どもが容易に想像できる自分の誕生日や電話番号、住所などにしないこと
・クレジットカードを紐付けたアカウントからは必ずログアウトしておくこと
・クレジットカードを子どもの目の届く場所に放置しないようにすること
が挙げられます。
また、クレジットカードやキャリア決済の明細を毎月確認することも忘れないでください。先ほどもお話したように、明細を確認していなかったことで長期間に渡り、子どもがゲームに課金し続けていたという課金トラブルのケースもあります。
お小遣いでプリペイドカードを購入してゲーム内で課金していることもあるので、小学生を含む子どもの利用状況はしっかり見守る必要があるでしょう。
ペアレンタルコントロール機能で小学生の子どもがゲームを遊ぶ時間や課金を管理

高橋: スマホや課金ができる家庭用ゲーム機には、課金や遊ぶ時間を制限するペアレンタルコントロール機能というものが備わっています。親御さんがスマホやゲーム機の機能を理解して、課金の制限や遊べる時間を設定することも大事です。「スマホやゲーム機の操作が苦手」という親御さんもいらっしゃるかと思いますが、その場合は、お父さんが苦手ならお母さんが、お母さんが苦手ならお父さんが、おふたりとも苦手なら詳しい友人や知人に頼るなど、「苦手だから」とあきらめずにペアレンタルコントロール機能を活用して、課金トラブルを回避してください。
簡単!ゲームが苦手な親のための課金トラブル対策
子どもの課金トラブルを未然に防ぐためには、子どもが使うゲームやスマホ、ゲーム機について理解することも大事だと語る高橋さん。子どもを持つ親御さんは特に、親が子どもの遊ぶゲームについて事前に知っておくべきことを、さらに詳しく伺いました。
小学生の子どもが遊んでいるゲームを親も遊んでみる
――ゲームが苦手だったり、興味がない親御さんが知っておくべきことについて教えてください。
高橋:
何度も繰り返しますが、重要なのは子どもが「ゲームに課金したい」という気持ちを頭ごなしに否定するのではなく、その話を聞いて理解してあげることです。「スマホやゲーム機は苦手」と拒否する例にも通じますが、「ゲームはやらないから」と理解をあきらめずに、子どもが楽しんでいるゲームに触れてみてください。
例えば、オンラインで多くのプレイヤーと一緒に遊べるゲームでは、自分が操作するキャラクターの見た目が小学生の子どもにとっては非常に重要です。あるゲームではログインするたびにキャラクターの見た目が変わることがあり、初期の見た目だと、他のプレイヤーと見分けがつかず、円滑なコミュニケ―ションができなくなり、仲間外れにされてしまうこともあります。課金することで見た目を好きな状態に固定できるため、友だちに認められたくて課金したい子どもがいるのです。
――アバター(見た目)は、ゲームを通じたコミュニケーションにおいて大事な要素だと思いますが、実際に遊んでみないとその重要性がわからないですよね?
高橋: そうですね。ゲームを遊んでみないとわからないことが多いですが、親もゲームを少し遊んだだけで理解できることもあります。例えば課金を制限している家庭でも、子どもから「友だちと遊ぶためにキャラクターの見た目を変える課金をしたい」という訴えがあった時、その目的を理解した上で、「見た目を変える課金はしてもいいよ」と許可してあげることができます。
わからないことは子どもに聞いてみよう
――親がゲームをプレイする際、普段ゲームをプレイしていないとわからないことが多いかもしれませんが、その場合はどのような対処方法がありますか?
高橋: 一番良いのは子どもに聞くことです。子どもは自分が好きなことについて話せることを喜びますし、普段偉そうにしている親にゲームのことを教えてあげることで優越感を覚えることもあります。ゲームを通じて、子どもとより深くコミュニケーションをとることもできるようになります。
子どもの課金トラブルが発覚。その時、親がとるべき対応は?
課金トラブルを防ぐための方法について高橋さんに伺いましたが、実際に課金トラブルが起きてしまった時、親がどう対応するべきかについても教えていただきました。
親と子どもで課金トラブルの原因を確認し、新たなルールを作る
高橋:
頭ごなしに叱らず、なぜ課金トラブルが起きてしまったのか理解し、子どもと話し合うことが大切ですね。もし親のクレジットカードが使用されてしまった場合、カードの管理が杜撰だった親にも問題があるかもしれません。
「ゲームへの課金は悪いこと」と決めつけず、子どもの話をしっかり聞いてあげてください。その上で、トラブルが起きてしまったら、課金に関する約束事をあらためて作り直し、「課金したい時は必ず相談する」といった最低限のルールを作ることが重要です。
頭ごなしに叱ったり、「ゲームへの課金は悪いこと」と決めつけすると、子どもはこっそり課金する可能性があるので、否定せずにしっかりとルール作りをするようにしてください。
早めに消費生活センターへ相談しよう
――課金トラブルが高額になった場合、子どもとの話し合い以外に親ができることはあるのでしょうか?
高橋: まず、早めに消費生活センターに相談してください。小学生や未就学児童が誤って課金してしまった際には、未成年者契約取消が認められることもあります。どうしてもケースバイケースにはなってしまうと思いますが、全国に消費生活センターという相談窓口があることは知っておいていただければと思います。
※未成年者契約取消の対応は各企業、お客様の状況などによって異なります。必ず返金されるものではございません。まずは消費者生活センター、利用サービスの各企業にお問合せください。
課金ルール作りには、子どもの気持ちの理解を大切に
最後に、小学生の子どもの課金トラブルを防ぐため、ガンホーが公開している『親子でスマホとゲームのお約束メイカー』を高橋さんに体験していただきました。
『お約束メイカー』なら悩まずに課金ルールを作ることができます

高橋:
これまで小学生を含む子どもの課金トラブルについて様々なところで講演してきましたが、「親子でゲームや課金についてのルールを決めてください」とお伝えしても、「何をどう決めたらいいのかわからない」と悩む親御さんもたくさんいらっしゃいました。
その点、『お約束メイカー』は、小学生の子どもと一緒にゲームや課金の具体的なルールを作っていけるところが良いですね。『お約束メイカー』で子どもと一緒に作ったルールは、親御さんが一方的に決めたものではないので、子どもも納得して受け入れることができますし、冊子にしてプリントアウトもできるので、親子で手軽に再確認できるのもメリットだと思います。
ゲームなどの課金に関するルールを決める時、一番大事なことは子どもの気持ちを理解してあげることです。『お約束メイカー』は、その手助けになると思いますので、子どもの課金トラブルに遭った親御さんや、ゲームに関する不安を抱かれている親御さんにはぜひ活用していただければと思います。
- POINTまとめ
-
- 小学生による課金トラブルは増加の一途を辿っている
- クレジットカードの管理を徹底して、課金トラブルを防ぐ
- ペアレンタルコントロールを活用し、ゲームの時間や課金を管理
- 子どもが「ゲームに課金したい」と思う気持ちを理解する
- 親と子どもが納得できるゲームや課金のルールを一緒に作る
 インタビュアー/ライター
インタビュアー/ライター
斎藤 ゆうすけ- さいとう ゆうすけ。ライター・放送作家。大学在学中よりゲームメディアで記事の執筆を行い、現在はテレビやラジオの放送作家として活動。バンタンゲームアカデミーおよび東放学園映画専門学校にて、講師としてゲーム関連の講義も担当しており、バンタンゲームアカデミー高等部eスポーツ専攻ではプロゲーマーを目指す高校生向けにネットリテラシーの講義も行う。活動に関する告知はX(旧Twitter)『斎藤ゆうすけ(アニゲウォッチャー)』にて発信中。