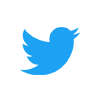受験本番も間近なのに、勉強しないでゲームばっかり! 本人にはその自覚がないのかしら!
まだまだ目の前のことしか考えられない受験生の中学生も多いのかもしれんのぅ……
- 親野 智可等さん

-
教育評論家。本名、杉山桂一。長年の教師経験をもとに、子育て、しつけ、親子関係、勉強法、学力向上、家庭教育について具体的に提案。『子育て365日』『反抗期まるごと解決BOOk』などベストセラー多数。人気マンガ「ドラゴン桜」の指南役としても著名。Twitter、Instagram、YouTube、Blog、メルマガなどで発信中。オンライン講演をはじめとして、全国各地の小・中・高等学校、幼稚園・保育園のPTA、市町村の教育講演会、先生や保育士の研修会でも大人気となっている。 Twitter、Instagram、YouTube、Blog、メルマガ、講演のお問い合わせなどについては「親力」のHPから。
受験生なのに「勉強したくない」と言って、勉強しないでゲームや動画視聴ばかり。このままでは成績も伸びなくて、合格できない!?と頭を抱えている親御さんも多いのではないでしょうか?今回は長年の教師経験をもとに、多くの媒体で子育て情報を発信されている教育評論家・親野智可等(おやの・ちから)さんに、厳しい受験勉強と楽しいゲーム・スマホとどう向き合うべきか伺いました。中学生の反抗期も重なる中、受験という親子で臨む大きな岐路で後悔しないためにも、ぜひ参考にしてください。
受験生である中学校3年生という時期を理解する
高校受験があり、反抗期でもある中学校3年生とはどのような時期なのか、尋ねました。
脳のアクセルは成長するが、ブレーキは不十分な時期
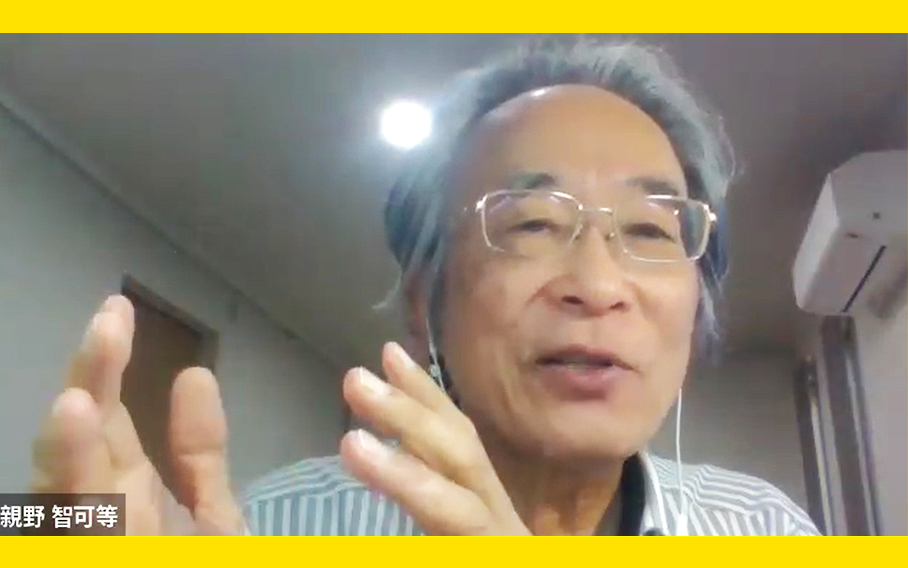
親野:
中学校3年生がどのような時期か、親側で理解しておくことが、非常に重要です。
発達心理学を研究されている京都大学の森口佑介先生によりますと、中学生になると小学生の頃より、自我も出て、力もついてくるので、やりたいこと、欲求が大きく増えるんです。ですが、欲求を抑えるブレーキ役の脳の「前頭前野」は十分に成長していないため、キレやすくなってしまうんですね。多くの受験生もこの影響を受け、中学生時代は非常に多くの感情と向き合うことになります。
――ブレーキが利かないまま、アクセルだけが大きくなってしまう時期なのですね。
親野: はい。ただでさえ中学生は勉強や部活動などの負担も増え、脳の発達が不安定な上に、この時期は友達にどう見られるかなど、周りからの評価が非常に気になる時期です。さらに今はSNSも発達しているから、余計に友達や同年代の動向が気になる。それに加えて受験勉強もしなければならないので、日々ストレスがいっぱいなのです。その中で、ゲームも誘惑として存在し、勉強したくないと感じることも多いでしょう。
中学校3年生は「個人差」が大きい
親野:
中学校3年生を理解するにおいて、「個人差がとても大きい」というポイントを頭に入れておく必要があります。学力も、やる気も、自己管理力も差があり、中学校3年生だからと一概には言えないのです。幼い子も早熟な子もいます。
「受験」という人生の大きな節目を目前にしていますが、中学校3年生では、目の前のことしか考えられない子どもも、まだまだ多いのです。「子どもが人生を長期的な視野で見られるようにするには、どうしたらいいでしょうか」と親御さんから時々聞かれるのですが、なかなか難しいですね。その子の成績や成長ペースがありますので、無理に勉強を強制するのではなく、それぞれの子どもに合った方法を見つけていくことが大切です。
子どもの受験勉強「やる気スイッチ」を押すには親は何をすればいい?
――中学生の受験生を抱える親としては、成長ペースを待たないといけない一方で、受験も迫ってきています。勉強したくない中学生の勉強の「やる気スイッチ」を押すために、親ができることはあるのでしょうか。
人生設計について親子で話す

親野:
子どもの受験勉強をはじめとした、勉強の「やる気スイッチ」を押すのは本当に難しい、永遠のテーマです。その前提で、親ができることとしては「○○高校合格」にとどまらず、「今後、あなたがどういう生き方をしたいか」という人生設計を親子で話すのはとてもいいと思います。
勉強したくないと反抗期中の子どもが急に人生設計を話すのは難しいかもしれませんが、親子で人間同士として、これからについて受験生の時期に会話をするのは貴重な経験になります。そのときは、子どもがはっきりとしたことが言えなくても、そういう経験をすること自体が1つのきっかけになりますから。
――親の人生設計を伝えてもいいかもしれませんね。
大人にもお勧めの「とりあえず方式」
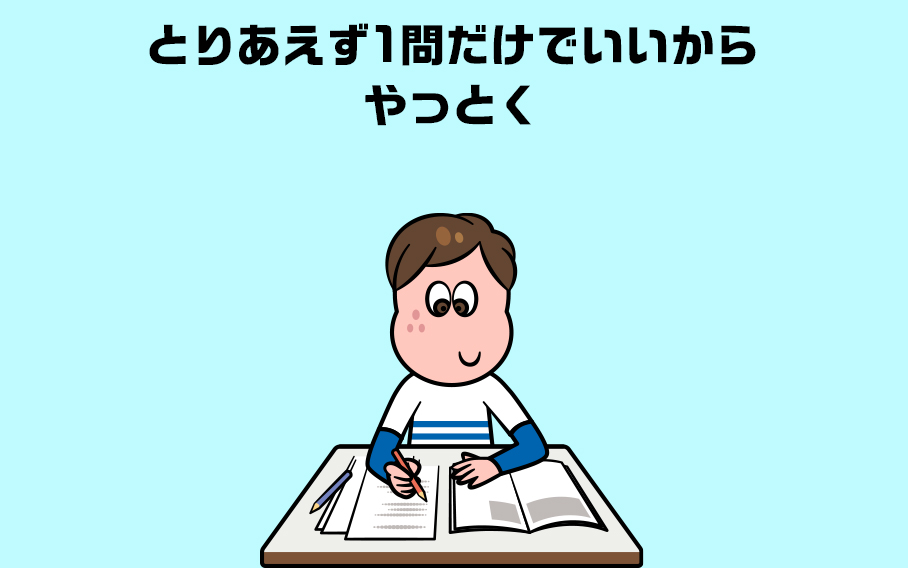
――子どもに勉強を促すための具体的なテクニックがあれば教えて欲しいです。
親野:
「とりあえず準備方式」をお勧めします。中学生の受験生が学校や塾から帰ってきたら、
① とりあえず宿題や勉強に必要なものを、机の上に出す。
② ①ができたら、とりあえず、やるページを開いておく。
③ ②ができたら、とりあえず一問だけやってみる。
数学のプリントだったら「1問だけやってみる」、書き取りなら「一字だけ書いてみる」などです。
必要なものを準備したり、1問だけやったりすると全体の見通しがつきます。すると、ゲームや休憩後に本格的に勉強に取りかかる時のハードルが下がるんです。脳科学者の方も「やる気スイッチはやり始めると入る」と言っています。だからまずは「とりあえず準備だけ」、「とりあえず1問だけ解く」ことが効果的です。
私自身も整理整頓が苦手で、食後に「とりあえず1個捨てる」断捨離を続けていますよ。すると、ついでに2個、3個とか捨てられるんです。まずは、「取りかかるハードルを極限まで下げること」がポイントです。
――確かに「やるまで」がおっくうなんですよね。 大人でも「とりあえず方式」は使えそうですね。
ゲーム好きな中学生の受験生に親がやりがちなNG対応
ゲームに夢中な中学生の子どもが気がかりなあまり、逆効果の対応をしていないでしょうか。受験生時期の反抗期の子どもと親の価値観の違いから考えていきます。
ゲームに関する価値観は親子で真逆
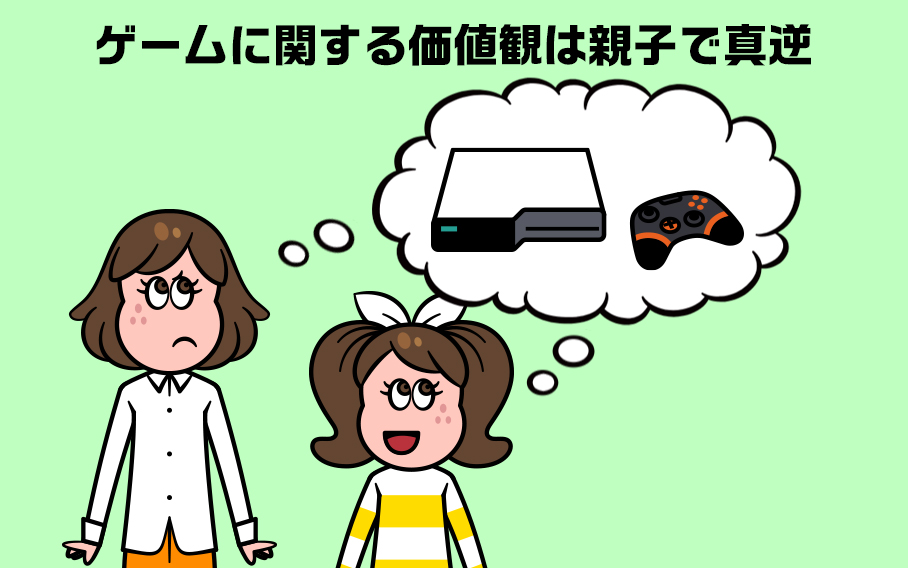
親野:
親と中学生の子どものゲームに対する価値観は、全然違うんですよね。子どもたちにすれば、ゲームはとにかく楽しいし、受験勉強のストレスや、成績の不安などの嫌なことも忘れさせてくれる。またゲームでは目標を設定して、それに向かって自分で工夫したり、クリアできると達成感を得られて、自己肯定感も上がります。現実の生活、特に受験生としての生活では、日々目標を達成するというのも、なかなか難しいですよね。さらに大勢の中学生がゲームを楽しんでおり、ゲームは子ども同士の話題の中心でもあります。
でも、親の立場からゲームを見ると、時間ばっかり費やして、受験勉強をしないだけでなく運動もしないし、お金や人間関係も心配になってくる。とにかくトラブルやリスクが心配で、できるだけゲームをやらせたくない。この真逆の価値観が原因で、ゲームをきっかけに親子関係が悪化しかねないんです。
大切なのは親からの歩み寄り
――ゲームの価値観が親子で大きくずれる中、親はどうすればいいでしょうか。
親野:
たとえ受験生の中学生であっても、親側から子どもに歩み寄って欲しいですね。「ゲーム、楽しそうだね」と、まず子どもに伝えてみる。そうすると、反抗期の中学生でも心を開き、一気にしゃべりだす子どもも多いですよ。ゲームのことだと熱心に話すのも、それだけゲームに時間もエネルギーも気持ちも入れ込んでいる証と言えます。なので、親は「楽しそうだね」「よく工夫しているんだね」と、中学生の子どもの話を肯定的に聞きましょう。 もし、子どもが「みんなやってるから、自分もやってないと話についていけない」と子どもが言ったら、「確かにそうだよね」と共感してあげましょう。また、ときには子どもにゲームのやり方を教えてもらったり、少しの時間でも一緒にゲームを楽しんでみたりするのもいいですね。
ゲームを厄介な受験勉強を妨げるものと見るのではなく、親子関係のコミュニケーションの手段にしてほしいです。ゲームについて、課金や利用時間など心配事も当然ありますが、それを子どもに伝えることができるのは、親が子どもの話を肯定的に聞くコミュニケーションが日々取れてからです。
――急がず、まずは信頼関係を構築するために、親側から子どもに歩み寄っていくことが大切ですね。
約束づくりは「共感的、民主的な対話」で行う
親野:
ゲーム・スマホに限らず、あらゆる親子の約束づくりでは「共感的かつ民主的な対話」がポイントです。親が「ゲーム・スマホは1日1時間!」と子どもに言うのは、対話ではなく親からの命令で、反抗期の中学生にはまず守られないでしょう。このような約束づくりは、親の自己満足に過ぎません。
「共感的かつ民主的な対話」とは、外交交渉のようなものですね。主張するところは主張するけれど、主張ばかりでは解決しないから、互いに譲ったり着地点を見つけたりしていく。例えば、「……じゃあ、そこは譲ってその時間でいいけど、その代わり宿題が全部終わってからやるという条件にしよう」というような感じで着地点を見つけていきます。
親が子ども扱いするから、子どもじみた反応が返って来る
――しかし、反抗期の中学生に「共感的で民主的な対話」はできるのでしょうか。
親野: 親が中学生を子ども扱いすると受験生としての自覚が芽生えず、勉強したくないという気持ちも相まって不満が溜まってしまい、いつまでも子どもじみた反応になってしまうんです。親子であっても中学生の子どもと大人は対等であり、人間同士リスペクトしあう関係を持つことが大切です。
――中学生を子ども扱いするから、子どもじみた反応が返って来て、それが受験生としての成長も妨げる……、という悪循環ですね。
親野: はい。特に反抗期に入った中学生に対しては、親は子どもを対等な1人の人間として対応してあげることがとても大切になります。親がリスペクトをもって対等に接することで、子どももそのリスペクトに応えようと心が成長し、受験生としての意識も芽生えます。
親子の約束をホワイトボードに記入する理由
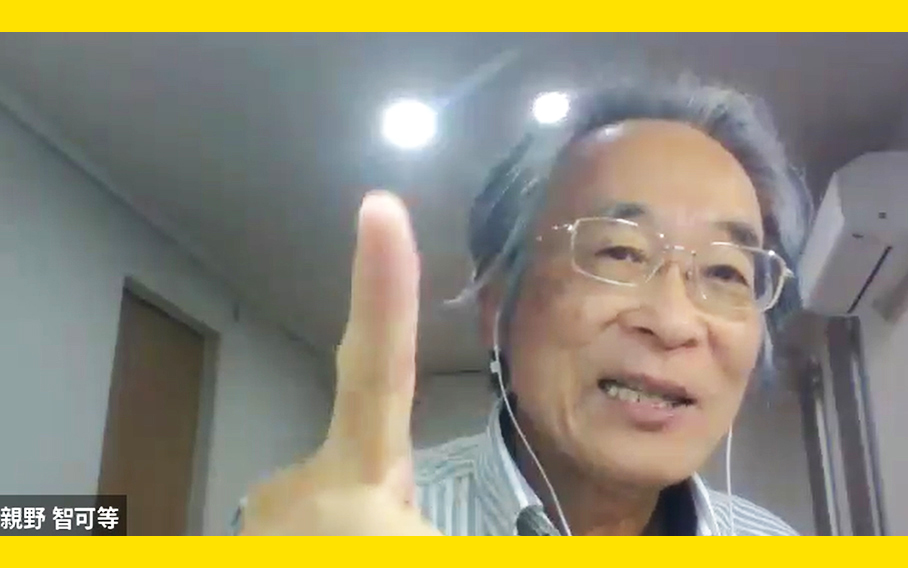
親野:
そして、受験生としての目標も含め、親子で作った約束は書かないと忘れるのでホワイトボードに書きましょう。ホワイトボードを勧める理由は他にもあり、勉強の計画や、ゲームの約束を実際に書いて運用すると「これは無理だな」みたいなことが絶対出てくるんです。
肝心なのは、そこで「どうするか」です。「いいからとにかく守れ!」ではなく、「うまくいかないね、実態に即していないね」とまた共感的、民主的な対話で約束を修正し、ホワイトボードを書き直す。これが中学生との約束を作り直す上で、とっても大事です。
面倒な「共感的で民主的な親子の対話」をして欲しい理由
――「共感的で民主的な対話」、大事なのは分かるのですが、大変そうですね……。
親野:
面倒くさいのですが、ぜひやってほしいですね。というのも、今回はゲームについてのお話ですが、子育てではさまざまな難題やトラブルが親子の前に出て来ますから。
例えば、学校の成績が振るわないとか、いじめられた、いじめた、喧嘩をした、もう学校行きたくないとか、塾を辞めたいとか、友達のモノを壊したとか、友達に万引きしようと誘われたとか……。 この先、高校生になってもいろいろなトラブルが出てきます。
このような非常時にも、「共感的で民主的な親子関係」があれば、子どもは「うちの親は話を聞いてくれる。一緒に考えてくれる」と思えるので、早い段階で親に相談できます。ですが、こういう関係が構築されていない場合、子どもは親に叱られることを恐れて言い出せません。そうなると、問題が大きくなってから発覚してしまいかねません。
親がゲームやスマホを制限するデメリット
――親が一方的にゲームやスマホを制限することについてはどうでしょうか。
親野:
子どものゲーム機・スマホを没収する、時には壊してしまう、といった「実力行使」はお勧めしません。これは「相手が言うことを聞かないときは、暴力的な方法で解決すればいい」と親がお手本を見せているのと同じです。
さらにまずいことに「実力行使」は一定の効果があるため、今度は子どもが家庭や学校で別のトラブルに遭遇した時に、親から学んだ「実力行使」に出る可能性は高まるでしょう。私はこれを「裏の教育」と呼んでいます。ですので、どんなに頭に来ても、そういう暴力的対応に出てはいけないんですね。
イライラして、子どもにキツイ言葉を言ってしまったときはどうする?
――子育てではイライラしてしまうこともあり、親であっても子どもに対して暴力的な言葉でキレてしまうこともあると思います。「やってしまった!」というとき、どうリカバリーすればいいでしょうか。
親野: 気づいた時に、すぐ謝るのがいいですね。「ごめんね。今ひどい言い方しちゃったね」と。これは絶対大事です。またそもそも、そうしたキレ方をしないためには、「アンガーマネジメント」で検索して、自分に合ったアンガーマネジメント方法を2,3個みつけておくといいでしょう。
――まずい、と思ったら深呼吸するとか、「ちょっと席を外すね」と一時離脱するのもよさそうですね。
共感的で民主的な約束づくりの導入に活用
――お約束メイカーの感想について教えてください。
親野: このようなツールはきっかけ作りになるので、非常にいいですね。ただ中学校3年生の場合は、中学生らしく民主的な対話のもとで約束が作られるといいのかなと思います。
- POINTまとめ
-
- 親子間に横たわる「ゲームの価値観のズレ」は親が歩み寄って
- 子ども扱いするから、子どもじみた反応が返って来る
- 「とりあえず方式」で勉強へのハードルを下げて
 インタビュアー/ライター
インタビュアー/ライター
石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter(X)『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂