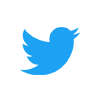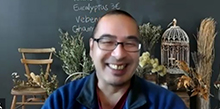子どもが反抗期に突入!ゲームやスマホのやりすぎを注意しても、さっぱり言う事を聞かないわ!
「言う事を聞かせる」というアプローチだと、親子ともにへとへになってしまうゾィ!反抗期の子どもとの関わり方にはコツがあるんじゃ!
- もくじ
- 増田 貴久

-
公認心理師・精神保健福祉士・ASK認定依存症予防教育アドバイザー 中学時代に不登校やゲーム依存を経験。大学卒業後にゲーム会社に就職。
その後、依存症専門治療機関にて依存症治療プログラム開発や個別カウンセリング、依存症家族教室開催、アメリカでの依存症研修などを経験。
現在はフリーランスとして、ASK依存症アドバイザー研修の講師や、ゲーム依存・不登校に関する家族支援講座、個別相談支援などを実施している。
今までは、親の言う事を素直に聞いていた我が子が、思春期・反抗期に入った途端、全く言う事を聞いてくれなくなった…そんな悩みを抱える親御さんは多いのではないでしょうか。
特に、勉強の妨げになると感じるゲームやスマホの「やりすぎ」は、親として最も頭を悩ませる問題の一つです。「少しは勉強したら?」「いつまでゲームやってるの!」と声をかければ「うるさいな!」と強い言葉が返ってくる。部屋にこもってスマホばかり見ていて、昼夜逆転気味になっている。成績は下がる一方で、この子の将来はどうなってしまうのかと、不安で夜も眠れない…。そんな反抗期の子どものゲーム・スマホのやりすぎ問題は、親の干渉が逆効果になることも少なくありません。
今回は、ご自身もゲーム依存を経験された公認心理士・精神保健福祉士の増田貴久さんに、思春期・反抗期の子どもと上手に付き合っていくための具体的な方法を伺いました。反抗期の子どものゲーム・スマホ問題で悩んでいる親御さんは、ぜひ参考にしてみてください。
子どもの反抗期はなぜ起きるのか?「ゲーム」「スマホ」への没頭の意味
そもそも、なぜ反抗期は起こるのでしょうか?親に反発し、ゲームやスマホの世界に没頭する子どもの心理的なメカニズムについて尋ねました。
12歳は子どもではなく「青年」。大人の入り口にいる

——反抗期は何歳ぐらいから始まるのでしょうか。
増田:女子は小学校4、5年生あたりから兆候が見られますね。男子は全体的に女子より1、2年遅れる傾向があり、中学校1、2年生あたりが反抗期のピークかなと思います。
——反抗期は、子どもの成長に必要なものなのでしょうか。
増田:その質問にお答えするために、まず人間の生涯にわたる発達についてお話しますね。 心理学者のエリク・ホーンブルガー・エリクソンは、人生を8つの発達段階に区切り、その中の「青年期」を12歳から22歳と定めています。
——12歳に「青年」のイメージはありませんでした。私たちが思うより、ずっと早く大人へのステップを踏み始めているんですね。
増田:はい。12歳は大人の入り口なんです。ただ、実際の中身は、まだ子どもが8割、大人が2割ぐらいのアンバランスな状態でしょうけれど。この時期の子どもたちは、心と体の急激な変化に戸惑いながら、大人でも子どもでもない自分に不安定さを感じています。
12~22歳の青年が乗り越えなくてはいけない課題とは?
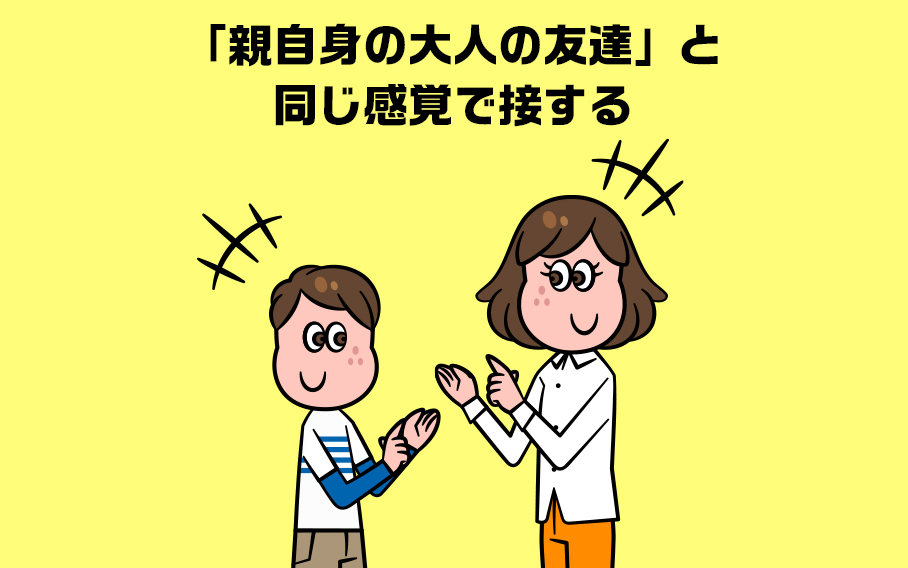
増田:そして、エリクソンは各発達段階には乗り越えないといけない「課題」があると提唱しており、青年期の課題は「アイデンティティの確立」になります。
——よく聞く言葉ではありますが、アイデンティティについてあらためて教えてください
増田:「自分とは何者か」「自分はどう生まれ、どう死ぬのか」「何が好きで何が嫌いなのか」「何がやりたくて、何がやりたくないのか」といった、自分自身の核となる価値観や生きる指針を見つけることです。青年期は、こういったことを自分自身で決めていく非常に重要な時期です。
逆から言えば、「誰かに言われたから、それに従う」こと、例えば「親に勉強した方がいいよと言われたから勉強する」という状態は、真のアイデンティティではありません。
もちろん12歳になったからといって、急に「僕は、私は、こう生きて行く!」とアイデンティティが確立するわけではなく、多くの青年は苦しみ、さまよい、時には親から見て「変なこと」もいっぱいして、紆余曲折の中もがき苦しみながらアイデンティティを確立させていきます。この青年がさまよう期間を心理学では「モラトリアム(猶予期間)」といいます。
——「大人」がはじまりつつも、まだまだ「子ども」であり、自分探しの旅でさまよう時期が青年期なんですね。そうなると、いわゆる「黒歴史」的なものも、このモラトリアムの産物とも言えそうですね。
増田:まさしくその通りです。そして、このモラトリアム期に子どもがゲームやスマホに没頭するのには、彼らなりの理由があります。ゲームの世界で仲間と協力して目標を達成したり、スマホを使って自分の好きな情報を集めたり、SNSで自己表現したりすることは、彼らが「自分とは何か」を探るための重要な活動の一部なのです。大人の目からは「やりすぎ」に見えても、それは彼らがアイデンティティを模索する中で、熱中できる対象を見つけた結果とも言えるのです。
青年期と受験が重なってしまう日本
増田:本来、青年期は社会からある程度守られたモラトリアムの中で、じっくりと自分と向き合い、さまよう時間が必要です。しかし、日本の教育システムでは、この最も多感で不安定な時期に、中学、高校、大学受験という大きなプレッシャーがのしかかります。
モラトリアムの最中で「自分は何をしたいのか」とさまよう青年に対し、親が「良い学校に行って、良い会社に入ってほしい」といった価値観を押し付け、干渉してしまう。それに対し青年たちが「自分の人生は自分で決める!」と反発したり、キレたりする。これが、多くの家庭で見られる反抗期の正体だと思います。特に、受験勉強というやらされ感の強いタスクから逃れるための避難場所として、ゲームやスマホが「やりすぎ」と言われるほど利用されやすくなるのです。
思春期・反抗期の子どもへ!ゲーム・スマホのやりすぎに悩む親の上手な接し方
大人の入り口に立ち、自我に目覚めた思春期・反抗期の青年に、親はどう接していけばいいのでしょうか。ゲームやスマホのやりすぎを、力ずくでやめさせる以外の方法を探ります。
12歳を過ぎた青年は「親自身の大人の友達」と同じ感覚で接したい

増田:思春期・反抗期に入った青年との接し方ですが、基本は「親自身の大人の友達」に対するのと同じ対応でいいと思います。例えば、ご友人と意見が食い違った時、頭ごなしに否定したり、自分の意見を押し付けたりはしませんよね。まず相手の話を聞き、なぜそう思うのかを理解しようと努めるはずです。
一方で、思春期の親子喧嘩の始まりは、親側の「こうしようって言ったのになんでしないの」「こうしなきゃダメでしょ」「どうしてそんなこともわからないの」といった、子どもをコントロールしようとする言葉が非常に多いんです。でも、大人の友達相手に、こんな高圧的な態度はとれないですよね。反抗期の子どもは、このような「子ども扱い」に最も敏感に反発します。
「好きにしたら、あなたの人生なんだから」
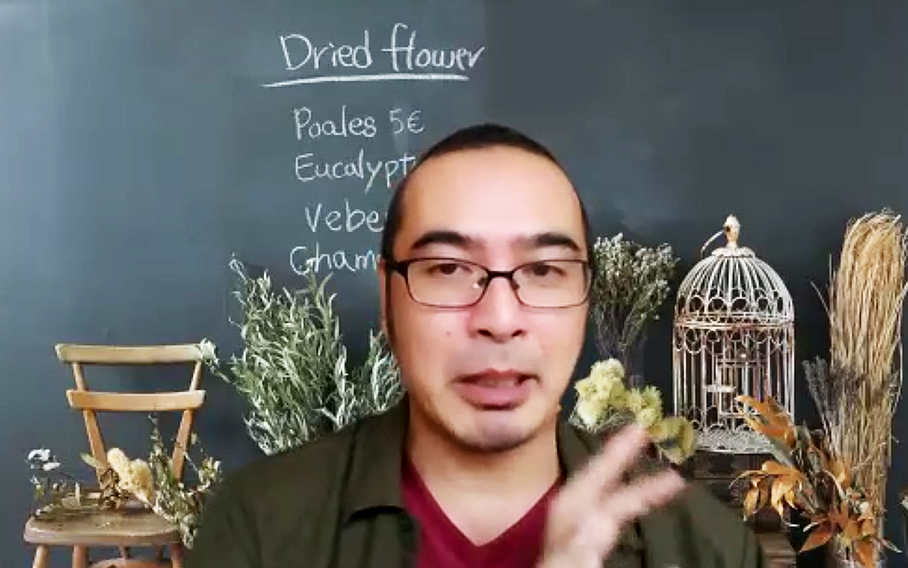
——しかし、友達と同じように接して、子どもがゲームやスマホのやり過ぎで好き勝手に生活してしまっては、親としては心配です。
増田:もちろん、放任とは違います。重要なのは、子どもにはゲームやスマホをする権利もあるが、「その選択によって生じる責任は、最終的に子ども自身が負う」ということをはっきりと伝えることです。ここだけを明確にするのが、12歳からの子育てでは手っ取り早いですし、親も精神的に楽になると思います。
「ゲームのやりすぎでテストの点が悪くても、スマホに夢中で寝不足になっても、その結果を引き受けるのはあなた自身だよ。好きにしたら。あなたの人生なんだから私は知らないわよ」と、親に突き放されると「これはまずいぞ」と子ども自身が自分の行動を客観的に見つめ直し、考え始めるきっかけになることも多いのです。
——確かに、ガミガミ毎日言われるよりも、信頼して任される方がドキッとしますし、責任感が芽生えそうですね。
互いの違いを許容できる親子関係を
増田:思春期・反抗期より前の、子ども自身に物事を判断する力が十分に備わっていない時期は、親がルールを決めて導くことも必要です。しかし思春期以降は、親は子どもを「自分の所有物」としてではなく、「自分とは価値観が全く違う、一人の独立した人間なのかもしれない」という視点で見つめ直すことが、良好な関係を築く鍵となります。基本は、大人同士の人間関係だと思いましょう。
——思えば、大人同士の人間関係でも、「あの人とは考え方が違うな」とお互いに思いつつも、うまく付き合っていることはありますよね。
増田:ですよね。お互いに「ちょっとここは…」と思うことはありつつも、相手の良い所も知っていて、リスペクトがあるからこそ、基本的には良好な人間関係を続けられる。親子だって全く同じです。親が子どものゲームやスマホのやりすぎを「無駄なこと」と切り捨てるのではなく、「この子にとっては大事な時間なのかもしれない」と一度立ち止まって考えてみることが大切です。
子どもの「ゲームやスマホの取り上げ」「勉強しない問題」への正しい対処法
基本的な親子関係の方針について伺ってきましたが、反抗期の子育てで特に問題になりがちな「ゲーム・スマホのやりすぎ」と「勉強」という具体的なケースについて、さらに詳しくお聞きしました。
思春期・反抗期の子どもからスマホ・ゲームを取り上げると?
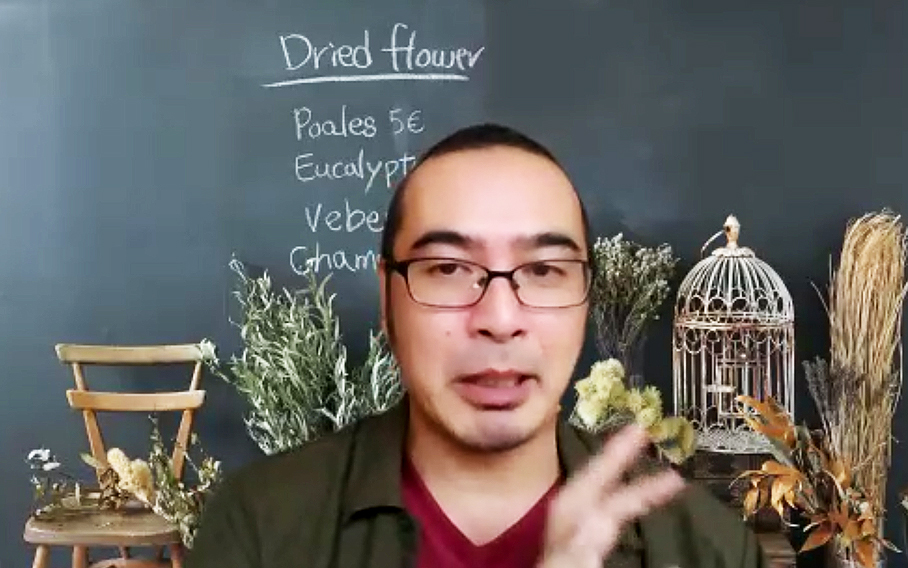
——今までのお話からすると、反抗期の真っ只中にいる子どもから、力ずくでスマホやゲーム機を取り上げるというのは、最も避けるべき対応に思えますね。
増田:はい、その通りです。スマホやゲーム機を取り上げるのは無駄ですし、百害あって一利なしだと思います。中古の端末は子どもでもお小遣いで買えますし、友達から使わなくなったスマホを譲ってもらうなど、親が知らない抜け道はいくらでもありますから。
本当に怖いのは、そうやって親に隠れてスマホを使う状況です。親子の信頼関係が崩れているため、万が一、ネット上で架空請求、パパ活や闇バイトといった犯罪に巻き込まれたり、SNSいじめに遭ったりといった、本当にまずい状況に陥った時に、子どもは親に助けを求めることができなくなってしまいます。
これがスマホやゲーム機を取り上げる最大のデメリットです。このリスクを上回るメリットが「取り上げること」にあるかといえば、残念ながら無いのです。
もし、熱中しているのがゲームやスマホでなく、ギターだったらどうか
——一方で、ゲームやスマホばかりやりすぎていたら、子どもの将来が心配だ、という声も根強いですよね。
増田:それは、ゲームやネットに対する親御さん世代の偏見や知識不足も一因かもしれません。ここで少し視点を変えてみてほしいのですが、もし子どもが夢中になっているのが「ギター」だったら、どう感じますか?
——ギターに熱中する10代なんて、まさに「青春」というイメージで、応援したくなりますね。
増田:ほら、ギターだと好ましく感じますよね。その熱中が、今の時代の子どもたちにとっては、たまたまゲームやスマホになっただけなんです。彼らはゲームというデジタルの世界の中で、仲間とつながり、試行錯誤し、達成感を味わうという、リアルな青春を過ごしているんです。
私自身もゲームが大好きで、時には「ちょっとやりすぎたな」と後悔することもあります。でも、この一見「無駄」に見える時間も、実はモラトリアムの一部なんです。親にとっては無駄で非生産的に思える時間も、その子の人格形成やストレス発散に必要なプロセスである場合もあるので、そこはぜひ長い目で見てあげてほしいですね。
「ゲーム・スマホvs勉強」でなく、根本は勉強の問題
——「子どもがゲーム・スマホに夢中で勉強しない」というのも、反抗期の子を持つ親の永遠のお悩みです。
増田:そうですね。しかし、よく考えてみてください。「ゲーム・スマホの時間を減らしたら、その分を勉強に充てるか?」と言われれば、かなり疑問が湧きませんか?多くの場合、子どもはただ別の娯楽を見つけるだけです。つまり、これはゲーム・スマホの問題ではなく、本人が勉強に対して意欲を持てていないという、純粋な「勉強の問題」だと切り分けて考えるべきです。
そもそも、勉強が心から好きで、自主的にどんどん取り組める子どもは、全体からみればごく少数派のはずです。
——確かに、大多数の子どもは、どちらかと言えば仕方なく勉強していますよね。
増田:大多数の、勉強がそこまで好きではない子どもにとって大切なのは、勉強するためのモチベーションをいかに自分で見つけていくか、ということです。「推し活」など、自分の好きなことが勉強の原動力になっているケースは意外と多くあります。「大好きなアイドルのコンサートに行くために、東京の大学を目指す」とか、それで十分立派な動機です。ゲームやスマホだって、モチベーションになり得ます。「海外のプレイヤーとゲームで話したいから英語の勉強を頑張る」「自分でゲームを作りたいからプログラミングを学ぶ」といった形で、好きなことが学びの入り口になることもあります。
「何のために勉強するのか」を悩むこと自体が、アイデンティティの確立のために非常に重要なプロセスです。「そんなことは考えなくていいから、とにかく勉強しなさい」と親がその機会を奪うのではなく、ぜひ一緒に悩んであげてほしいですね。何より、「良い大学に行く」以外の選択肢だって、いまの時代には無限にあるのですから。
思春期以降に結んでおいた方がいい約束はたった1つ
増田:これまで色々とお話してきましたが、日本の社会は子育てにおいて、あまりにもお母さんの責任が大きすぎる傾向にあります。 「お前の育て方が悪いんだ」と、周囲から、時には自分の夫からさえも責められてしまう。これはどう考えてもおかしいので、お母さん自身がその呪いを解いていくことも、すごく大事です。子どもは家庭だけでなく、社会全体で育てていくものですから。
——そのような中で、反抗期を迎えた思春期以降の子どもと、最低限これだけは結んでおいた方がいい、という約束はありますか?
増田:思春期以降は、基本にはもう「大人同士」の関係なので、あれもこれもと細かくルールで縛る必要はないと思います。
ただし、「命にかかわること、法を犯すこと、そして取り返しのつかないデジタルタトゥーに繋がるようなネットリテラシー」については、親子でしっかりと価値観を共有し、約束として確認してほしいですね。
例えば、安易な気持ちで悪ふざけの動画をSNSに公開したり、自分の性的な画像を誰かに送ってしまったりすれば、デジタル情報として一生涯消えずに残り、その後の人生を大きく狂わせてしまう可能性があります。親は心配のあまり、あれもこれもと口うるさく注意したくなりますが、そうすると子どもは親の言うことを一切聞かなくなってしまいます。本当に重要なことだけを伝えるために、余計なことは言わない。それが、反抗期の子どもとの信頼関係を保つ秘訣です。
- POINTまとめ
-
- 12歳からはもう「大人」の始まり。反抗期の子どもには、親も大人同士の対等なやり取りを意識する
- 子どものゲームやスマホを「取り上げる」ことは、問題を隠蔽し、より危険な状況を招く可能性がある
- 思春期・反抗期以降の親子の約束は、「命と安全」に関わる最低限のものに絞り、あとは本人の責任と自覚に任せる勇気を持つ
 インタビュアー/ライター
インタビュアー/ライター
石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter(X)『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂