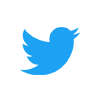ゲームのチャット機能で子どもは悪い大人と会うんだから、チャット機能を使えないようにすればいいんだわ!
別の問題を呼ぶかもしれんゾイ!
- 佐々木 雄希さん

-
2013年 慶応義塾大学理工学研究科 博士課程修了。 警察官であった父親が設立した危機管理コンサルティング会社、株式会社セーフティ・プロの取締役副社長として学校の危機管理や警備業務に従事した後、学校で犯罪が起きない環境づくりを支援するため、2017年に一般社団法人スクールポリスを設立。 スクールポリス設立以降、情報化や多様化が進む学校において、SNSやネットの利用によるトラブル事例やその対策についての講演を行っております。
ゲームやスマートフォンを通して、小学生などの未成年の子どもたちが思わぬトラブルに巻き込まれたり、重大な犯罪の被害に遭ったりするというニュースを、日常的に目にする親御さんも多いのではないでしょうか?特に、オンラインゲームでの見知らぬ人との出会いや、SNSを介した交流がトラブルに発展するケースは、親御さんにとっても大きな心配の種になっていることでしょう。今回は、こうしたインターネット上のトラブルや犯罪など「見えない脅威」に対し、教育機関への指導やパトロール活動を行っている警察OBで組織された一般社団法人スクールポリスの佐々木雄希さんに、実際に子どもたちの間で起きているゲームやスマホ関連のトラブル、そしてゲームをきっかけとした出会いや犯罪に発展する実態などについて、詳しく伺いました。お子さんが楽しく、そして何よりも安全にゲームを楽しむため、そしてインターネット社会で身を守るために、ぜひ参考にしてください。
子ども同士がトラブルになる理由とは?親の介入はどこまで必要?
オンラインゲームやスマホアプリを通じて、子ども同士でトラブルが多発しています。なぜこのようなトラブルが起きてしまうのか、そして、親がどこまでトラブルに介入すればよいのか、その適切な距離感について佐々木さんに尋ねました。
子ども同士のトラブルのきっかけは「ローカルルールを守らない」ことから始まる
——ゲームやスマホ、SNSなどを通じて、子ども同士で起きやすいトラブルには具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
佐々木:ゲームやスマホに限った話ではありませんが、子どもたちの間には、大人にはなかなか見えにくい「ローカルルール」というものが存在したりしますよね。例えば、「このゲームではこのキャラクターは使っちゃダメ」といったような、仲間内だけのルールです。それを誰かがルールを破ると「あいつは分かってない」「ルールを無視している」といった感情が生まれやすくなり、それがきっかけに言い合いや喧嘩につながるのが非常によくあるケースです。
こうした傾向は、小学校の中学年くらいから高学年あたりにかけて顕著になり始めます。そして、中学生、高校生といった思春期に入ると、さらに深刻化することがあります。例えば、ローカルルールを破った人をSNS上で「晒す」といった、より陰湿な形でのトラブルに発展するケースも報告されています。
——今にして思えば、私たちも子ども時代に、大人から見れば些細なことと思えるようなローカルルールを巡って揉めたり、いざこざを起こしたりしましたね。ゲームを巡るローカルルールも、子どもにとっては非常に重要なものなのですね。
佐々木:はい。そして、こういった一見些細に見える子ども同士のトラブルが、その延長線上に「いじめ」など、より深刻な事態にまで発展してしまうケースも少なくありません。
子ども間のトラブル時、親はどう介入する?「ゲームでの出会い」に危険がある場合は即介入を

——ゲームやスマホを通じて、子どもたちの間でのトラブルが発覚した時に、親がどう介入するかというのも、非常に悩ましい問題だと感じています。どこまで口を出すべきか、どのタイミングで介入すべきか、判断が難しいです。
佐々木:何でもすぐに親が介入していくのは、基本的にはあまり好ましくないかと思います。子どもが自分で解決する力を育む機会を奪ってしまうことにもなりかねません。まずは、子どもの話をじっくりと聞いてあげて、その上で、親はあくまで助言を与えるというスタンスで関わってみてください。お子さんが自分で考えて、解決策を見つける手助けをしてあげることが大切です。
一方で「子ども間のトラブル」という範疇を超えた、親が即座に介入しなければならないケースも明確に存在します。例えば「子どもがオンラインゲームで知り合った人と、実際に会おうとしている」などは、親がすぐ介入しなければいけません。これは、インターネット上の出会いが現実世界での危険な出会いに繋がる典型例です。特にお子さんがまだ小学生や中学生といった年齢の場合は、判断能力が未熟ですから、気付いたら迷わずにすぐに介入してください。重大な犯罪につながる可能性もあります。
悪意ある大人は、ネット上で子どもをどう騙す?出会いの手口に要注意
ゲームやスマホを通じて、悪意のある大人が子どもを狙い、事件に巻き込むケースが後を絶ちません。そういった大人の巧妙な「手口」はどのようなものなのか、特にゲーム内での出会いからどのように子どもに近づいてくるのかを尋ねました。
大人が本気になれば、インターネットの世界では子どもは簡単に騙せてしまう

佐々木:悪意のある大人が、どのような手口で子どもを騙そうとするのか、オンラインゲームを例にとって具体的にご説明しましょう。最近のオンラインゲームは、ほとんどのものがチャット機能を備えています。このチャット機能は、ゲーム仲間とのコミュニケーションに非常に便利ですが、悪意ある大人はこれを悪用します。彼らは、毎日、何時間も、何十時間も、子どもたちと一緒にゲームをプレイし、チャットで交流を重ねていくのです。
何時間、何十時間とオンライン上でやり取りを続けていると、たとえ一度も会ったことがなくても、子ども達の間には「もうこの人はゲームの仲間だ」「信頼できる人だ」という認識が生まれてしまい、強固な信頼関係が形成されてしまいます。この信頼関係が築けたところで、悪意のある大人は「ゲーム以外のところでお話しよう」とLINEなどの個人連絡先を聞き出し、1対1でやり取りできるように誘導します。その中で、身近な人や友人には相談しづらい個人的な悩みなどを巧みに聞き出し、「君の写真を送ってほしいな」とか「今度、実際に会って一緒にゲームしない?」などといった具体的な誘いを持ちかけてくるんです。
ですので、これは特定の手口というよりも「大人が本気になって子どもを騙そうとしたら、インターネットの世界では子どもは簡単に騙せてしまう」という現実を理解しておくべきです。特にゲームの世界でピンチの時に助けてもらったり、親切にしてもらったりといった経験があると、子どもは相手を「恩人」「頼れる人」と強く信頼してしまう傾向があります。時として、ゲームでの出会いから生まれる信頼は、現実以上に強く感じられることもあるため、注意が必要です。
——私たち大人はインターネット上の知り合いとリアルの知り合いの間に明確な線を引いて考えることができますが、子ども、特に小学生や中学生には、その線引きが非常に難しいのですね。
チャット機能を完全にオフにすれば解決!…ではない複雑な問題

——ゲームのチャット機能が悪意ある大人と子どもが出会うきっかけになるのならば、いっそのことチャット機能を完全にオフにしたり、あるいはチャットの相手は子どものリアルな友達のみに制限したりするのはどうでしょうか。そうすれば、ゲームでの出会いから危険な目に遭うリスクを減らせると思うのですが。
佐々木:親御さんがそう考えるお気持ちはよくわかります。しかし、ゲームのチャット機能を完全に制限してしまうと、子どもは強い不満を持つ可能性があり、それが親子関係の悪化につながってしまうことも考えられますね。
お子さんのリアルの友達の中には、チャット制限などをされずに自由にゲームをしている子どもも当然いますよね。今のゲームは、チーム戦や対戦形式のものが非常に多いので、そういったゲームではチャット機能がチームメイトとの連携や作戦を立てる上で、とても頻繁に使われます。そのため、チャット機能を使えなかったり、親に制限されていたりすると、ゲーム内のチーム戦の進行に大きな影響を与え、ゲームの勝敗にも影響が出てしまうことがあります。
——「チャットが使えないあの子がいるからチームが勝てない」「あいつがチームにいるとゲームが面白くない」といった雰囲気になってしまうと、お子さん自身がゲーム仲間から浮いてしまったり、仲間はずれにされたりする可能性も出てきてしまいますね。
佐々木:はい。冒頭で、子ども内での「ローカルルール」からの逸脱が子ども同士のトラブルに繋がりやすいとお話しましたが、「チャットが使えない」という状態も、ある意味では「ローカルルールからの逸脱」になりかねません。したがって、「チャットは危ないから、完全に蓋をしましょう」と一律の対応だけでは、必ずしも最善の解決策とは言えないと考えています。子どもがゲームを通じて社会性を学ぶ側面もありますから、バランスが重要です。
チャット自体は悪いものではない。大切なのは「何かおかしい」という危機意識
——ゲームのチャット機能との付き合い方は、非常に悩ましい問題ですね。では、親として、一体どうしたら良いのでしょうか。また、ゲームでの出会いの危険性をどのように子どもに伝えれば良いでしょうか?
佐々木:まず、大前提として認識していただきたいのは、「知らない人とのチャット」自体は決して悪いことではないということです。インターネット上には、純粋にゲームを楽しんでいる善良なユーザーが大勢いますし、たいていの人は問題なく、適切にチャット機能を使っています。オンラインゲームでの出会いが、全て危険な出会いに繋がるわけではありません。
親御さんが最も警戒すべきだと子どもに教えたほうが良いのは、相手が「実際に会おう」と誘ってきたり、「LINEを交換しよう」「個人的な写真を送ってほしい」「本名や年齢、最寄り駅などプライベートな情報を教えてほしい」などと、「個人情報」や「現実世界での出会い」を引き出そうとしてきた時です。その時に「この相手は何かおかしい」「いつもと違う言動だ」と、最大限の警戒心を持たなければならないと、具体的に子どもに教えることが非常に大切です。
また、どうしてもお子さんが「ネット上の友達と会いたい」と強く言うような場合は、「会うのは絶対ダメ!」と頭ごなしに禁止してしまうと、子どもは強く反発し、親子の信頼関係が揺らいでしまう可能性があります。そうではなく、親御さんから「じゃあ、お母さん(お父さん)も一緒にその人に会いに行ってもいいかな?」と提案してみるのも良い方法です。
その時に相手が「え、親は来ないでよ」「なんで親が来るの?」と拒んだり、連絡が途絶えたりすれば、「ああ、この人はやっぱり悪意を持った大人だったんだな」と、子ども自身もその相手の本質を理解できますよね。子ども自身が悪意を察知する力を育む良い機会にもなります。
「ネット上の人と会ってしまう」以外にどんなトラブルがあるのか
ここまでは、オンラインゲームを通じた出会い、つまり「会ってしまう」系のトラブルを中心に伺ってきましたが、その他に、ゲームやインターネットを介して子どもたちが巻き込まれる可能性のあるトラブルにはどのようなものがあるのか、佐々木さんに尋ねました。
自分のゲームのIDとパスワードを人に教えるのは規約違反であり、深刻なトラブルに繋がる
佐々木:「実際に会う」こと以外のトラブルとして、子どもがゲームのIDとパスワードを悪意ある大人に教えてしまうケースも非常に多くみられます。これも、オンラインゲームを介した出会いから生じるトラブルの一つとも言えます。
ゲームを通じて信頼関係ができてしまうと、「君が学校に行っている間に、君のキャラクターのレベルを上げておいてあげるよ。IDとパスワードを教えてくれれば、代わりにゲームを進めてあげるから」といった甘い言葉で誘われると、子どもはあっさり教えてしまうんですね。特に小学生などの判断能力が未熟な子どもは、こうした誘いに乗りやすい傾向がみられます。しかし、それが大きな落とし穴です。せっかく時間をかけて育ててきたゲームのIDやアカウントが、勝手に売られてしまったり、パスワードを悪意ある第三者に変更されてしまい、お子さん自身がそのゲームにログインできなくなってしまったりする事態に発展します。さらに最悪の場合、「ゲームにログインしたかったら金を払え」と、金銭を要求する脅迫に発展するケースも報告されています。
——ゲームのIDやパスワードは、多くのゲームの利用規約で他人に教えることを禁止しています。そのため、もし教えてしまったことで起きたトラブルは、ゲーム会社による救済措置が受けられないケースも多いと聞きます。子どもにその危険性をどう伝えれば良いか悩ましいです。
ID・パスワードをひとつ知られれば、芋づる式で他のサービスも乗っ取られる恐怖

佐々木:なお、これは子どもだけでなく、大人でも思い当たる人が多いと思いますが、実はパスワードを複数のサービスで使いまわししているケースが非常に多いですよね。もし、1つでもゲームサービスのパスワードを悪意ある第三者に教えてしまうと、芋づる式に全て乗っ取られてしまう可能性があります。
——それは怖すぎますね!まさかゲームのIDとパスワード1つで、そんなに広範囲に被害が及ぶなんて、子どもには想像もできないでしょう。
佐々木:そうなんです。IDとパスワードは、実際のモノとして目に見える形がないので、子ども達はその重要性を認識しにくく、こういったトラブルになりがちなんですよね。私たち、一般社団法人スクールポリスが学校で講演をする際には、「ゲームのIDとパスワードを他人に教えるのは、<自分の家(自宅)の住所と家の鍵>を、一度も会ったことのない人に渡してしまうことと全く一緒」だと伝えています。例えば、「君が学校に行っている間に、家の片付けをしておいてあげるよ」と言われて、一度も会ったことのない人に、自宅の住所を教えて、家の鍵も渡してしまうのと同じくらい危険な行為なんだよ、と具体的に説明することで、子ども達もその重大さを理解しやすくなります。もちろん、パスワードを使いまわさないことも、トラブルを防ぐ上で非常に大切です。
「なんか危ないぞ」の「なんか」が大きなトラブルを防ぐ!危機意識を育成する大切さ

——ここまで、様々なお話を伺わせていただき、ゲームやインターネットに関するトラブル、特にゲームでの出会いがもたらす危険性について心構えができました。最後に、ガンホーの「お約束メイカー」についての感想をお聞かせください。
佐々木:こういった、親子でゲームのルール作りをサポートする取り組みは、本当に大切だと思います。ただ、一度約束を作って「これで終わり」にしてしまうと、子ども達もだんだんとその約束を忘れていってしまいますので、日々の生活の中で、作った約束を繰り返し親子で振り返ることも非常に大切ですね。
「繰り返し振り返る」というプロセスを通じて、子どもの中で「あれ、なんかまずいぞ」「このゲームでの出会いはちょっと危険かもしれない」という「危機意識」が自然と育っていくようになります。具体的に「何がどう危険なのか」を理論的に説明できなくても、「なんか危ないとか、授業で言ってたよな」や「親とゲームの約束を振り返ったときに気を付けようと話したよな」という漠然とした「なんか」で十分なのです。この「なんか危ない」「なんか変だ」という感覚、つまり直感的な危機察知能力こそが、いざという時のブレーキとして非常に強力に働くことになりますから。
- POINTまとめ
-
- 子ども同士が揉めるのは「ローカルルールからの逸脱」
- 大人が本気になれば子どもは簡単に騙せる
- IDとパスワードは「住所と家の鍵」!
 インタビュアー/ライター
インタビュアー/ライター
石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter(X)『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂