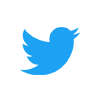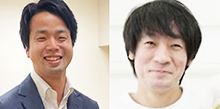時間の約束を決めたのに子どもがゲームを終わらせない!キイ—!必殺・電源オフよ!
ムム……、あまり良い結果にならんかもしれんゾイ……
- もくじ
- 森山沙耶さん

-
ネット・ゲーム依存予防回復支援サービスMIRA-i(ミライ)所長 公認心理師、臨床心理士、社会福祉士 2012年、東京学芸大学大学院教育学研究科修了。家庭裁判所調査官を経て、病院・福祉施設にて臨床心理士として勤務。 2019年、ネット・ゲーム依存予防回復支援サービスMIRA-i(ミライ)を立ち上げ。当事者とその家族に対するカウンセリング、予防啓発のための講演、執筆活動を行う。 著書に『専門家が親に教える子どものネット・ゲーム依存問題解決ガイド』(2023年7月Gakkenより発売)
小学生の子どもがゲームばかり…「ゲーム以外に興味がない我が子が心配」「ゲーム依存かも」と悩む親御さんへ
「うちの小学生の子どもがゲームばかりしていて、他の事に全然興味を示さない…」「もしかして、このままゲーム依存になってしまうのではないか」と、深く心配されている親御さんも多いと思います。親としては、何とかゲームの時間を減らして「やめさせたい」という気持ちが募る一方、どうすれば良いか分からず悩んでしまいますよね。今回はゲーム依存に詳しく、数多くの相談を受けてこられた臨床心理士の森山沙耶さんに、お子さん自身がゲームと上手に付き合うための大切なコツや考え方を伺ってきました。
小学生の子どもがゲームをなかなかやめない時…親がゲーム機の「電源を切る」のは効果がある?ない?
小学生のお子さんが、親との約束の時間を過ぎてもゲームをなかなかやめない、もっと続けたいと訴える。そんな場面に直面したとき、カッとなってゲーム機の「電源を切る」ことを選択した、あるいは強くそうしたい衝動に駆られた親御さんも少なくないかもしれません。多くの親御さんが直面するこの難しい瞬間に、一体どう対処すればいいか具体的なアドバイスを伺いました。「ゲームをやめさせたい」一心での行動が、逆効果にならないためのヒントがあります。
「ゲームの電源を切る、取り上げる」行為が、子どもとの関係を壊し最悪の事態を招くことも

——親子でゲームの約束を決めているのに、小学生のお子さんがゲームをなかなかやめてくれない場合、保護者はどのように声をかけたらよいのでしょうか? 親としては「もう時間だよ!」「ゲームをやめなさい!」と言って、子どもが親の言うことを聞いてくれないと、どうしていいか分からなくなってしまいますよね。
森山:そうですね。親子喧嘩になってしまい、結果的に感情的になった親御さんがゲーム機の電源を一方的に切ってしまったり、ゲーム機を取り上げてしまったり、というのはよくあるケースとして耳にします。ですが、この方法は避けた方がいいと皆さんにお伝えてしています。多くの場合、お子さんの強い反発を招き、逆効果になってしまうケースが非常に多いためです。
この時のお子さんの状況を少し想像してほしいのですが、そもそもゲームというのは熱中して遊びますし、興奮しやすいものですよね。さらに、集中力も高まっている状態です。
——確かに、ゲーム中というのは熱狂、熱中、興奮、高い集中力を伴う状況ですね。
森山:その興奮して集中している状況で、何の予告もなく、あるいは感情的にその対象であるゲームを取り上げられたり、電源を切られたりしたら、どう感じるでしょうか。当然、強い怒りやイライラ、不満が湧きあがってきますよね。最悪の場合、親に対して手が出てしまい、暴力行為に発展した結果、警察や児童相談所が介入することになったケースも存在します。親子の安全が第一ですので、暴力につながる可能性がある場合などは、強硬手段を避けなければいけません。
子どものゲーム問題、親は「ひたすら我慢する」しかない?

——暴力という最悪の結果になることは避けなければいけないですね。しかし、親としては「ゲームをやめさせたい」のにやめてくれず、毎日イライラしたり、やめさせるための声かけに疲弊したり…親も我慢ばかりでは限界を感じてしまいそうです。
森山:親御さんから「結局、親が我慢しなきゃいけないんですか?」と尋ねられることがよくありますが、親であっても自分の気持ちを無理に我慢する必要はないと思います。「我慢しなきゃ」と思ってしまうと親御さんも辛いですよね。そんな時は、伝え方やアプローチの仕方などを工夫することで、親子双方が少し楽になれる方向を目指したいですね。
——具体的に、どういった方法で親も子もストレスなくゲームと付き合えるようになるのでしょうか。
森山:いくつかの方法があります。まず、「環境を整える」という視点です。特に小学生くらいの子どもは、一度ゲームに熱中すると時間の感覚がなくなりがちです。お子さんが自分で時間の経過を確認できるように、ゲームをする場所から見える所にタイマーや時計を置いておきましょう。 視覚的に確認することで、お子さん自身もゲームをやめる心の準備がしやすくなります。
次に親からの「声かけ」です。お子さんが「自分の好きなゲームを否定されている」と感じてしまうような受け取られ方にならないよう、伝え方を工夫したいですね。ここで有効なのが、主語を親御さん自身にする「私メッセージ」です。子どもを主語にした「(子どもであるあなたが)ゲームをやめなさい」という命令形ではなく、「(親である私が)夕食ができたから一緒に食べたいな」とか「ゲームの約束を守ってくれると(親である私が)安心するよ」と伝えるのです。そうすると言われたお子さんも「(あなたが)ゲームをやめなさい」と直接的に否定されるよりも、親の気持ちとして受け入れやすくなります。
そして、重要な視点ですが「ゲームをやめる」「ゲーム時間を減らす」ことだけを目的にしないことです。フォーカスするべきは、ゲームによって起こっている問題、例えば「ゲームのしすぎで成績が下ってしまった」「夜遅くまでゲームをして睡眠不足になっている」「ゲームばかりで友達と遊ぶ機会が減り、対人関係が希薄になっている」「家族との会話の時間が減り、家族関係が悪化している」といった、生活上の具体的な困りごとをどう解決していくかに焦点を当てることも大切ですね。
——なるほど。いっしょくたに「ゲームやネットが問題だから没収したり、時間を減らしたりすればいい」という考え方ではなく、ネットやゲームが原因で、お子さんの生活にどのような問題が起きているのかを細やかに、注意深く見ていくことが大切なのですね。
ゲーム以外に「これなら興味があるかも!」を見つけるには?依存を防ぐための多角的なアプローチ
ゲームに依存してしまう原因や、子どもが「ゲームだけ」にならないために、親御さんはどうサポートすればいいのか、さらに詳しく伺いました。
「気晴らしがゲームでしかできない」状態は要注意サイン。「ゲーム依存」の入り口かも…
——森山先生は、ゲーム依存の「原因」をどのように考えていますか? 親としては、「なぜうちの子はこんなにゲームにのめり込んでしまうんだろう」と悩んでしまいます。
森山:ゲーム依存の原因は、一つには絞れるほど単純ではなく大変難しい問題ではあります。ただ、依存に至るメカニズムの中で言われていることの中には、「ゲームがお子さんにとって、不安やストレスを緩和するための、気晴らしをするための【唯一の手段】になってしまっている状態」であるというのはあります。
——なるほど。問題なのは「ゲームそのもの」の良し悪しではなく、ゲームが「不安やストレスを緩和するための、他に代えのきかない【唯一の手段】になっていること」なんですね。
森山:はい、まさにその通りです。ですから、ゲーム以外にも自分自身の感情を上手にコントロールする方法、ストレス対処の方法、そして気晴らしの手段をいくつも持っておくことが重要です。
子どもの「好き」のヒントはゲームやYouTubeに隠れている!興味関心を広げる鍵
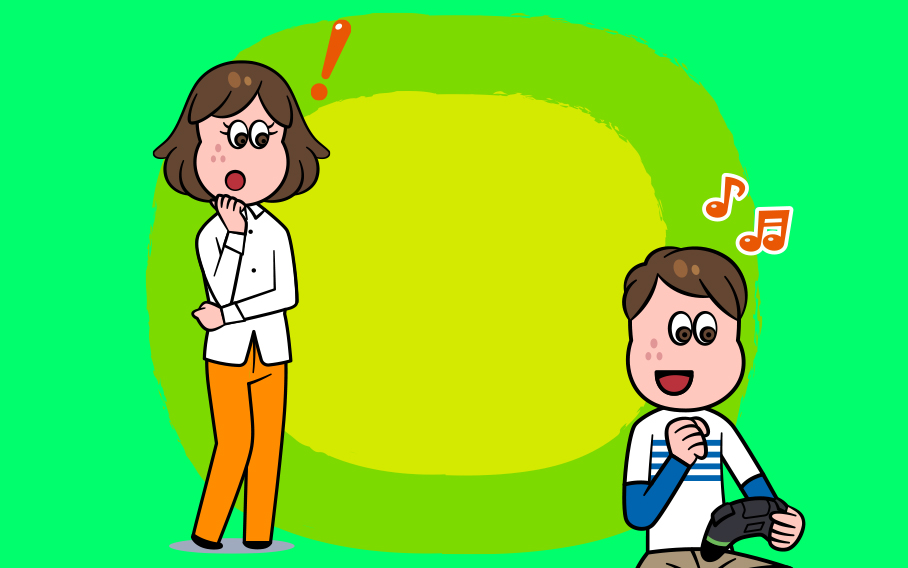
——ゲーム以外の気晴らしや興味を見つける、というのは理想ですが、現状ではゲームやネットにしかそれを見いだせないお子さんに対して、親はどのようにサポートしていけばよいでしょうか。
森山:お子さんが普段夢中になっているゲームや好きなネットのコンテンツなど、お子さんの「好き」の中には、その子の興味関心のパターンや心が満たされるポイントを見つけるヒントが隠されています。例えば、小学生のお子さんがシューティングゲームや戦闘系のゲームに熱中しているとしたら、それは「ハラハラ、ドキドキするスリル」を求めているかもしれません。「マインクラフト」のような、ゼロから何かを創造していくサンドボックス型のゲームが好きなら、自分で想像したものを「自由に作り上げる喜び」や、完成させたときの「大きな達成感」を求めていたりするのでしょう。また、チームを組んで協力するゲームが好きなら、「誰かとつながっていたい」といった傾向が読み取れます。ゲームに限らず、お子さんが好きなYouTubeのジャンルや漫画の内容、あるいはアイドルの推し活など、様々な「好き」でも、同じことが言えますよね。
——子どもが好きで楽しんでいる遊びやコンテンツの中に、そのお子さんを知る重要なヒントがあるということですね。
森山:はい。ですから、お子さんがゲームやネットに熱中しているときに、親御さんは「どうせ遊びなんでしょ」と頭ごなしに決めつけて終わりにせず、その子の「好き」を深堀りしてみる視点をもっていただきたいのです。スリルを求めるタイプならこれはどうか、とか、人とつながることで安心感を得られるならこれはどうか、など、お子さんの興味関心を広げるためのヒントとして、お子さんが好きなゲームやコンテンツを活用されると良いと思います。
ゲームやネット依存を防ぐ「お約束」の作り方 :親子で納得できるルールとは?
依存とは何か、そして依存を防ぐための考え方や方法について伺ってきましたが、最後に親子の良い約束の結び方について伺いました。
ゲームのルール「ゲームは毎日〇時間まで」だけではうまくいかないゲームもある?

——小学生のお子様のゲーム利用について、親子で約束を作るときに、どのようなポイントに気をつければ納得して守ってくれるようになるでしょうか?
森山:そうですね、ゲームの種類によって、効果的なルールの決め方は変わってきます。ゲームによっては「毎日〇時間まで」と時間で決めたほうがいいゲームもあれば、バトルロイヤル系のゲームのように1回のプレイ時間が勝敗によって変動するゲームでは、「1日〇回まで」のように回数で決めたほうがいいものもあります。お子さんが遊んでいるゲームの種類や特徴を話し合いながら、お子様自身も「キリが良い」と感じやすく、納得してゲームを終えやすい約束を見つけていくのがいいと思います。
そして、親の押し付けや強制、監視ではなく、お子様自身が時間を意識し、自分で決めた約束に従って、自分の意思で終える習慣ができるといいですね。私も7歳、4歳の子どもがいますが、自分たちで見る動画の本数を決め、見終わった後は終了ボタンを子ども自身に押させるようにしています。自分で「終わりにする」という行動を選択し、自分で「終了ボタンを押せた」という達成感を、子ども自身が積み重ねて育んでいくことが自己肯定感にもつながります。子どもは「認められたい」「褒めてもらいたい」という感情を持っているので、それを伸ばしてあげたいですね。
——最後に、ゲームのルール作りをサポートする、弊社運営の「お約束メイカー」の感想を教えてください。
森山:約束は親子で一緒に決めることが最も有効であるといわれている中で、お約束メイカーは、感情的に言い争ったり、険悪な雰囲気になったりすることなく、ポジティブに話し合うことを助けるツールになると思いました。
「約束を作る」と、ゲームをクリアしたような達成感も感じられるように工夫されているので、親子にとって「約束を作る」というプロセスが、億劫なことから良い経験としてのイメージに変わるのではないでしょうか。
- POINTまとめ
-
- 約束を守らないから電源ブチっ、では、お子さんもブチ切れる?
- 親だって我慢しなくていい、コミュニケーションを工夫しよう
- 子どもが好きなゲームには、子どもの興味関心のヒントがいっぱい!
 インタビュアー/ライター
インタビュアー/ライター
石徹白 未亜- いとしろ みあ。ライター。ネット依存だった経験を持ち、そこからどう折り合いをつけていったかを書籍『節ネット、はじめました』(CCCメディアハウス)として出版。ネット依存に関する講演を全国で行うほか、YouTube『節ネット、デジタルデトックスチャンネル』、Twitter(X)『デジタルデトックスbot』でデジタルデトックスの今日から始められるアイディアについても発信中。ホームページ いとしろ堂