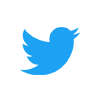ゲームをやめない子どもを見ているとイライラしちゃって、つい怒ってばかり。自己嫌悪になっちゃいそう……
上手な怒り方を覚えれば自己嫌悪に陥らずに済むのじゃ!
- もくじ
- 安藤俊介さんプロフィール

-
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事。アンガーマネジメントコンサルタント。新潟産業大学客員教授。 怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニング「アンガーマネジメント」の日本の第一人者。
アンガーマネジメントの理論、技術をアメリカから導入し、教育現場から企業まで幅広く講演、企業研修、セミナー、コーチングなどを行っている。 ナショナルアンガーマネジメント協会では15 名しか選ばれていない最高ランクのトレーニングプロフェッショナルにアジア人としてただ一人選ばれている。
主な著書に『アンガーマネジメント入門』(朝日新聞出版)、 『アンガーマネジメントを始めよう』(大和書房)等がある。
著作はアメリカ、中国、台湾、韓国、タイ、ベトナムでも翻訳され累計 70万部を超える。
ゲームを「何時までにやめる」と子どもと決めたのに、時間を過ぎてもゲームをやめない子どもにイライラしてしまい、ついつい厳しく怒ってしまった経験はありませんか?その結果、子どもを怒りすぎて自己嫌悪に陥ってしまったり、「親のイライラが子どもの成長に悪影響を及ぼすのでは?」と心配になったりと、思い悩んでいる親御さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
親のイライラした気持ちは、子どもにも伝わり、親子関係が気まずくなることもあります。ゲームが好きな子どもを持つ親御さんなら「子どもを怒らずにゲームをやめさせたり、自分のイライラや、怒りの感情をコントロールする方法があるなら、ぜひ知りたい!」と一度は思うものでしょう。そこで、今回は、日本アンガーマネジメント協会の安藤俊介さんに子育てにおける怒りのコントロールについて伺いました。
子どもがゲームばかりしていても、イライラしない方法はある
ゲームばかりしている子どもを見ているとイライラしてしまう自分をなんとかしたい…。その第一歩として、まず「怒り」の感情を理解するポイントを伺いました。
なぜ、親は子どもに怒りの感情を覚えてしまうのか?

——ゲームばかりしている子どもに対し、親がイライラしないで、怒らずにやめさせるにはどうしたらいいのでしょうか?
安藤:まずは、「怒る」とはどういった感情なのかを理解することが大切です。この「怒る」という感情は、すべての動物に備わっているものです。自分が大切にしている何かが侵害されたり、危ない目にあったりしている時に、それを守ろうとする感情が「怒り」です。親が子どもにイライラするのは、まさに親にとって大切な何かが脅かされていると感じている証拠なのです。このイライラの根源を理解することが第一歩です。
「親の怒りの原因」と「子どもにしてほしいこと」はリンクしている
——ゲームをやめない子どもにイライラしたり、「怒り」を覚えたりするのは、子どもがゲームをやめないために、親御さんが「何か大切なものを侵害されていると感じた」ということなんですね。
安藤:そうですね。例えば、「ゲームばかりで勉強しないと将来困るのでは」という心配や、「夜遅くまでゲームばかりしていて体調を崩すのでは」といった、ゲームへの「のめりこみ」によって、どんな事が危惧され、何が嫌なのか、親御さん自身が「怒り」や「イライラ」の原因を考えることで「感情に任せた怒り」を避けられるようになると思います。
親のイライラは、その根本にある不安や心配から来ていることが多いのです。このイライラの裏にある本当の理由を見つめ直しましょう。
——危惧される内容はご家庭によって様々だと思いますが、子どもにはイライラした感情をぶつけたくないと考える親御さんが多いと思います。親御さんが「怒りの原因」を理解した上で、どのように子どもと接するのが良いのでしょうか?
安藤:「怒り」の原因を理解したら、次に「怒り」の感情と子どもに「こうしてほしい」というリクエストとを分けて伝えることが大事です。ただ感情的に「ゲームをやめなさい!」と怒っても、それで子どもが委縮してしまい、無気力な状態になってしまっては困りますよね。親のイライラが子どもの行動を阻害することもあります。「怒り」の原因がわかれば、子どもへのリクエストも明確になるはずです。例えば、「怒り」の原因が「ゲームばかりで子どもが将来良い学校にいけないのでは?」という危惧、つまり「学業がおろそかになることへのイライラ」だとしたら、「ゲームは一日〇時間までならやっていいよ」と約束した上で、「その代わり、〇時間は勉強しようね」と、親子で妥協点を見つけることができるはずです。このように具体的な解決策を子どもに提案することで、親のイライラを減らし、親子で建設的な話し合いができるようになります。
子どもへのイライラを断ち切るには?自己嫌悪にならないために親ができること
怒りの原因を知る方法を基に子どもにどう伝えれば良いのか、具体的な例を挙げて語ってくださった安藤さん。続いて、子どもに対して怒りすぎてしまい自己嫌悪に陥ってしまった時の対処方法について伺いました。
子どもを怒ってしまった後の「やってしまった」感は、実に辛いものです。自己嫌悪に陥らないように、イライラを減らすことも非常に大切です。
カッとなったら「6秒ルール」と「大きく深呼吸」

——怒りの原因を理解していても、ついカッとなって子どもに怒ってしまい、その後に自己嫌悪に陥ってしまう親御さんも多いようですが、そうならならないためにはどうしたら良いのでしょうか?イライラの感情を鎮める有効な方法はありますか?
安藤:まずは、カッとなって怒ってしまうというシチュエーションをできるだけ減らすことです。私は「6秒ルール」と呼んでいますが、「カッとなった」あるいは「イライラしてきた」と感じたら、まず6秒待ってみてください。この時、大きく深呼吸をすることも大事です。その際、息を吐くことを強く意識すると良いでしょう。それにより筋肉が弛緩され、冷静さを取り戻すきっかけになります。たった6秒待つことで、衝動的な「怒り」や「イライラ」のピークを乗り越えることができるはずです。この小さな工夫で、大きなイライラを防ぐことができます。
「~すべき」や「~しなければならない」という言葉は危険信号
——カッとなって、子どもにイライラをぶつけてしまいそうになったら、深呼吸をしてまずは落ち着くことが大切なんですね。このイライラを放置しないことが重要だと感じました。
安藤:もちろん、深呼吸をする余裕もなく、感情に任せて子どもに怒ってしまうこともあると思います。それで自己嫌悪に陥ってしまう親御さんも多いと思いますが、世の中に完璧な人間なんていません。自己嫌悪に陥ってしまったら、そこからどう次に繋げるかが大事です。「今回のイライラから何を学ぶか」と考えるのです。どうしても感情的に怒ってしまうという親御さんは、ご自身が使っている言葉に注目してください。「~すべき」「~しなければならない」という言葉を日常的に使っていたり、頭に浮かんだりするようであれば、危険信号で注意が必要です。これは、自分のイライラが特定の思考パターンに囚われているサインで、この思考がイライラをさらに増幅させてしまうこともあります。
——「~すべき」や「~しなければならない」と断定してしまうと、子どもの意見を聞く余地がなくなり、子どもとの妥協点を探ることもできませんよね。親のイライラから、子どもに無理強いしてしまいそうです。
安藤:子どもには子どもの主張があるはずですが、「~すべき」や「~しなければならない」と断定してしまうと、親の主張を一方的に押し付けることになってしまいます。この「~すべき」や「~しなければならない」という考えを一度捨てないと、上手に怒ることができず、自己嫌悪に陥る負のスパイラルから脱け出すことはできません。このスパイラルは、自分自身はもちろん、周囲、つまり子どもも不幸にしてしまいます。親のイライラが子どもにも伝染してしまう危険性があるので、このイライラの連鎖を断ち切ることが大切です。
「叱る」と「怒る」の違いは?イライラしても一貫性を持つ重要性
「叱る」ことは正しくて、「怒る」ことはダメだとよく言われていますが、「叱る」と「怒る」に違いはあるのでしょうか?
子どもへの「イライラ」との向き合い方にも関わるこの二つの言葉について、安藤さんに考えを伺いました。
怒る上で大事なのは一貫性を持つこと
——よく「叱る」と「怒る」は違うと言われていますが、安藤さんは「叱る」と「怒る」の違いについてどうお考えでしょうか?親としては、感情的に「怒る」のは子どもに悪影響で、冷静に「叱る」ほうが良いのではないかと悩んでしまいます。
安藤:私は「叱る」と「怒る」を同じものとして捉えています。その上で「怒り」の感情と、その背景にある「相手へのリクエスト」を分けて考えることが大切だと思っています。そこで大事になるのが「一貫性」です。
子どもに対するイライラや怒りの感情が伝わらないよう、意識的に一貫した態度を取りましょう。
——一貫性とはどういった事なのでしょうか?親のイライラが子どもに伝わらないようにするためにも、具体的な例で教えていただけますか?
安藤:例えば、勉強せずにゲームばかりしている子どもがいたとしましょう。そういった子どもに対して、ある日、親御さんがついカッとなって感情的に怒ってしまったとします。しかし、別の日には自分の機嫌が良いからと「今日ぐらいは大目に見てあげるか」と怒らなかったらどうでしょう? 子どもから見て、決して一貫性がある行動とは言えませんよね。「怒られる」ことに一貫性がないと、子どももどうしていいかわかりませんし、「今日は親の機嫌が悪いから怒られただけ」と「怒られる」ことを軽視するようになってしまいます。親のイライラの度合いで対応が変わると子どもは混乱し、親の言葉の重みがなくなります。こうなってしまうと、いくら怒っても、子どもは言うことを聞かなくなってしまいます。そして、親のイライラも解消されず、悪循環に陥ってしまうでしょう。このイライラは、子どもの反発心を強めるだけです。
約束を守らない子どもに怒ってしまう・・・親のイライラを増幅させないためには?
せっかく親子でゲームの約束を作っても、守らずにすぐに破られてしまっては、親のイライラも増すばかりです。最初から約束を作らないという選択をしないための心構えを安藤さんに伺いました。
諦めないことと、頻繁に声かけを
——子どもと作った約束を破られてしまったことで、子どもとの「約束」を無駄だと感じてしまっている親御さんもいるようですが、「約束」について安藤さんはどうお考えでしょうか?
安藤:「約束」は一貫性を持って「怒る」ために必要なツールです。先ほどお話ししたように、子どもを怒る上で大事なのは「一貫性」です。「ゲームは一日〇時間まで」と「約束」したら、親御さんの機嫌が悪かろうが、良かろうが、「約束」を破った時は、一貫して同じように怒りましょう。そして「怒る」際には、感情的なものではなく、約束を破ったことへの冷静な対応であるべきです。これが、親のイライラを子どもにぶつけるのではなく、ルールを教えるという形になります。
——親が一貫した態度で怒り続けても、子どもの反応が薄かったら、「怒っても無駄」「イライラするだけだ」と諦めてしまう親御さんもいらっしゃるかと思いますが、そのあたりはどうでしょう?
安藤:諦めてしまってはコミュニケーションが成立しません。真面目な親御さんほど、膝を突き合わせて丁寧に話し合おうとする傾向がありますが、無理に長く話し合いの時間を持とうとするよりも、ちょっとした挨拶や軽い注意でもいいので、頻繁に声をかけることが大事です。特に中学生ぐらいの思春期に入った子どもは、親の話を聞きたがらないものです。それでも、例えどんなに煙たがられようが子どもに話しかけ続けることで、少しずつでも親御さんの想いは伝わっていくはずです。根気強く冷静に、そして継続的にアプローチすることが重要です。イライラに負けずに、向き合いましょう。
イライラ解消のための約束作りと「お約束メイカー」の活用がおススメ
最後に、子どものスマホ・ゲームのトラブル減少のため、ガンホーが公開している『親子でスマホとゲームのお約束メイカー』を安藤さんに体験していただきました。お約束メイカーが、親の「イライラ」を軽減し、子どもとの関係を良好に保つ上でどのように役立つのか伺いました。
『お約束メイカー』は、感情とリクエストを切り離せる

安藤:怒る時に重要なのは、感情と相手へのリクエストを切り離すことだとお話しさせていただきましたが、『お約束メイカー』は子どもへのリクエストを明確化する上で、大変すばらしいものだと思います。親のイライラが爆発する前に、具体的なリクエストを整理することができるので、イライラを軽減できる一助になるでしょう。
また、子どもと一緒に「約束」を作ることで、感情に任せて子どもを責めたり、落ち込ませたりすることなく、「親子で決めた約束だから守ろう」という冷静な話し合いができます。
『お約束メイカー』は、親がイライラを感じる場面を減らし、子どもとの建設的な関係を築くためにも有効なツールです。
ゲームばかりしている子どもに対し、つい感情に任せて怒ってしまうという親御さんは、ぜひ『お約束メイカー』を活用していただければと思います。
- POINTまとめ
-
- 怒りの原因は大切な何かが侵害されているという感情
- 感情と相手へのリクエストの切り離しが重要
- 「~すべき」や「~しなければならない」という感情に注意
- 一貫性を持って怒るようにする
- 子どもに無視されても諦めずに声をかけ続けるようにする
- 「約束だから守ろう」という冷静な話し合いが大事
 インタビュアー/ライター
インタビュアー/ライター
斎藤 ゆうすけ- さいとう ゆうすけ。ライター・放送作家。大学在学中よりゲームメディアで記事の執筆を行い、現在はテレビやラジオの放送作家として活動。バンタンゲームアカデミーおよび東放学園映画専門学校にて、講師としてゲーム関連の講義も担当しており、バンタンゲームアカデミー高等部eスポーツ専攻ではプロゲーマーを目指す高校生向けにネットリテラシーの講義も行う。活動に関する告知はTwitter『斎藤ゆうすけ(アニゲウォッチャー)』にて発信中。